■ 「ものづくり」の歴史と共に誕生・発達してきた原価計算

原価計算は、それを利用する企業の様々な原価観に基づいて、誕生・進化を遂げてきました。その道の大家、アドルフ・マッツは、「原価計算は、目的達成のための手段であり、それ自体、何らの目的も有しない」という言葉を残しています。われわれ、原価計算を学び、企業会計において実践する身としては、その原価計算をなぜやるのか、『目的』の理解にこそ意味があると心得るべきです。
それでは、原価計算の変遷を下記チャートに簡単にまとめてみました。

チャートを概覧いただき、お分かりになったと思いますが、原価計算には各種技法が存在しますが、そのいずれも、その時々の経済環境に対応するため、企業経営目的を達成するために編み出されたものです。それゆえ、「●●原価計算をやれば、原価情報を欲する全ての利用者の欲求を満たすことができる」というのは幻想にすぎないことが理解して頂けると思います。では、次章からその300年足らずの短い?歴史の糸を手繰っていきましょう。
■ 「産業革命」が原価計算を生み出した
家内制手工業から産業革命を経てしばらくは、各企業が製造・販売する製品の売価について、取引形態は個別受注生産方式が主流であったことから、その企業独自の価格決定の裁量がまだ大きいままでした。同時に、ミクロ経済学的に、当時の市場経済の状況から、
供給 ≦ 需要 (万年的な物不足)
的な供給者優位の市場だったため、経営者は、原価に一定のマージン(利益)を加算することで価格を決定する「コストプラス法」で値決めすることができました。それゆえ、当時の原価計算に課せられた使命は、売価決定のための正確なコスト積上げ計算だったのです。
当時の原価概念・利益概念は、
製造原価 + 適正利益 = 顧客提供売価
■ 見込生産方式による規格品の大量生産が原価管理を養成した
工場制工業による大量生産が普及し、生産形態が受注生産から見込生産に徐々にシフトしていくと、各企業は、プライスメイカーからプライステイカーに位置づけが変わり、独自の価格決定が困難になりました。そこで、市場競争で決まった売価を所与の前提として、その市場価格の中からより大きい利益を獲得するため、または市場から退出せずに済むように、コストダウンすることが求められました。
ここにきて、原価・利益概念は、
獲得利益 = 市場価格(売価) - 作り込み原価
では、原価管理を実践するために必要な原価計算技法とはなんでしょうか?
① 工程別原価計算
原価情報を原価管理に役立てるためには、原価の発生点において、原価を原価責任者別に把握されている必要があります。どこで発生した誰が管理している原価がどれくらいかを知るために、部門別・工程別の原価能率を図る必要があったのです。それは、徐々に複雑になっていった製造工程の多層化に伴うものでもありました。
② 標準原価計算
従来は、価格、能率、操業度など、原価に影響を及ぼす偶然的な変化に左右されて発生した歴史的原価(実際原価)を積み上げて、結果としての原価情報を積み上げていました。それでは、目標利益を獲得するための目標原価を達成するには神に幸運を祈るしかありません。そこで、当時一世を風靡したテーラーの科学的管理法に基づいた目標原価を、科学的・統計的に算出して「標準原価」と名付け、「実際原価」との差分を如何に詰めるかを、製造現場で追求する原価計算管理手法が一般的になりました。
③ 営業費計算
当初、原価管理はあくまで製造現場における製造原価の範疇のものでした。しかし、どんどん価格競争が激化し、製造原価を詰めていっても、販管費が水膨れのまま放置されていては、企業が当初目論んでいた利益を獲得することはできません。そこで、原価管理対象が製造原価から販管費を含む総原価に守備範囲を広げていくことになりました。ここで、営業費については、「注文獲得費」「注文履行費」などの機能費の分析が行われるようになりました。それゆえ、『原価計算基準』が対象とする原価概念は、販管費を含む「総原価」となっているのです。
■ 制度としての原価計算の誕生
生産形態が個別受注生産から大量見込生産へシフトし、原価計算目的も価格決定から原価管理にシフトしていきましたが、あくまでそれらの原価情報は生産現場で用いられるものでした。企業会計のディスクロージャー制度の根幹である複式簿記機構の埒外で管理されている数字だったのです。19世紀後半から20世紀前半にかけて、公認会計士による会計監査の重要性が認識され、一般会計の元帳によって統制され、その発生額の信憑性、売上原価と期末棚卸資産の区分について、信憑性のある会計数値として、財務諸表の一部に組み込まれることになりました。これがいわゆる「原価計算制度」の誕生というわけです。
ここでひとつ、大きな論点が生じます。元帳に基づいて統制される原価情報は、勘定連絡図に沿って、転がし計算による原価計算手続を厳守することを課せられます。費目別計算→部門別計算→製品別計算と、歴史的原価を順番に転がして計算していては、原価計算にかかる時間が膨大になり、決算発表に間に合わない恐れがあります。そこで、「原価標準」を用いて、サクッと原価計算をしてしまうという考え方も登場してきました。
しかし、「取得原価主義」「全部原価計算」の厳格なルールに基づいた発生主義会計の考え方に依拠すると、不可避的に発生する原価差額も何らかの処置で売上原価と期末棚卸価額に振り分ける必要があります。それゆえ、『原価計算基準』には、原価差額の取り扱いが含まれているのです。
■ 利益管理と予算管理のための原価計算
1929年、ニューヨーク州ウォール街で起きた株価大暴落を契機に世界大恐慌が起こり、各企業の経営者は、自社内における遊休設備の稼働率管理に頭を悩ませます。世界中で一瞬のうちに需要が蒸発し、そこかしこに遊休資産が溢れていました。世界中の企業が増強した生産力を持て余していたのです。ちみちみと目の前のコスト計算だけをやっていたのが、利益そのものの計算までが従来の原価計算の領域に持ち込まれたのです。それは、生産現場の効率化を増進していれば企業業績が何とかなっていた時代から、市場需要に合わせた生産能力の管理までをコスト計算でつなぎ合わせて利益創出をすることが経営者の使命になった瞬間でもありました。
① CVP分析
膨大な設備投資による過大な固定費負担(そのほとんどが減価償却費)をどうやって早期に回収して企業に利益をもたらすことができるか、商品ポートフォリオから人員配置まで、固定費と変動費のコストビヘイビアの分析結果から得られる示唆で意思決定し、損益分岐点を可視化することで営業量と生産能力のバランスを量るようになりました。
② 直接原価計算
外部公表用の財務諸表は全部原価ベースでの開示ですが、開示情報作成ルール(制度会計ルール)に従っていると、過去の経営判断によって不可避的に背負わされることになった固定費(キャパシティコスト)が、期末棚卸資産として次期の損益計算に繰り延べられてしまいます。そうした遊休資産にかかる減価償却費は、自己金融効果で資金の内部留保増加に役立ちますが、期間損益を過大に計上してしまい、一方で遊休資産処理の判断を遅らせる結果ともなり得ます。そこで、固定費発生額の全額を当期費用として見立てて、原価計算=期間損益計算をする手法が、経営判断(遊休設備の処分と採算管理)を行う際に有用なコスト情報を提供することがもてはやされたのです。
③ セグメント損益計算
直接原価計算における固定費は、複数事業・製品を製造・販売する際に、どれにいくらかかっているか個別にはわからない共通のコスト(共通費)としての性格も兼ね備えることが多いことが知られています。そこで、単体のセグメント(事業・製商品・組織・顧客カテゴリ等)は、直接費だけでいったん利益計算をして個別採算を求め、共通費は個別採算データ全体から控除して企業全体の採算を管理する手法が採用され始めます。世界恐慌の前後には、金融資本による巨大コンツェルンが複数事業を営んでいることもそう珍しくなくなり、そうした大企業の経営者は、自社内の複数事業・製商品の撤退や集中、時には事業や商権買収のための損益情報を従来の原価計算担当に求めたのです。
こうした利益管理のための各種計算技法が、「短期利益計画」という形で、企業の単年度予算制度に組み込まれていくことになります。その残滓が、現代にまで生き延びている年度予算制度であり、今でもその中心に据え置かれているのが「損益予算(P/L予算)」です。キャッシュフローや貸借対照表の単年度予算はおまけで、事業別・製商品別の損益予算がまだまだ企業予算制度の主役であることが多いのは、この時代の影響をまだ引きずっていると言っても過言ではありません。
■ 意思決定会計のための原価計算
つまるところ、会計監査の厳格化により、原価計算が制度会計報告に組み込まれて、「原価計算制度」と社内で公式化されたことにより、制度会計ルールに強く影響を受けたものに変容していきました。当初は、価格決定や原価管理のためのツールが、制度会計をベースにした短期利益計画(年度利益計画)や単年度予算制度に組み込まれていきます。標準原価は利益目標を達成するための前提条件としての目標原価として、予実管理を中心とする予算制度にしっくり合いました。
一方で、遊休資産の稼働不足による予定チャージレートが過大評価になること、つまり操業度不利差異が期末に多額に発生するかもしれないリスクを内包するため、制度としての原価計算(=予算制度)は、同時に、直接原価に基づく社内用の利益計画書の作成という二重の責務を課せられることも多くなりました。現在の製造業を中心に、制度原価計算(=全部原価計算)と、直接原価計算の二重管理を実践している企業が数多く存在しています。
さらに、企業を取り巻く外部環境の不確実性が高まり、単年度の利益目標だけを追っていては企業経営が成り立たなくなり、中長期の採算見通し情報の提供が求められるようになりました。その中で、設備投資の経済計算、事業買収における買収価値の算出、業務活動における執行のための判断(自製か購入か、製品ポートフォリオ、事業の撤退可否、新規事業参入の採算分析など)といった、期間損益計算構造の埒外で損益情報、中でもコスト情報を求める経営者が増えました。そうした判断材料の基となる原価データは、「特殊原価調査」と呼ばれ、「原価計算制度」では算出できない計算機構により、アドホックに求められるようになったのです。そうした企業内での意思決定は、各種「基本計画」として社内で策定された方針に基づき実行されるのでした。
こうしてものづくり企業の売価設定のための実際製造原価の積上げ計算技法が、企業経営のかじ取りのための判断情報を提供する採算情報作成のツールにまで発展した300年弱にわたる原価計算の歴史は現代まで続いているのです。お粗末様!







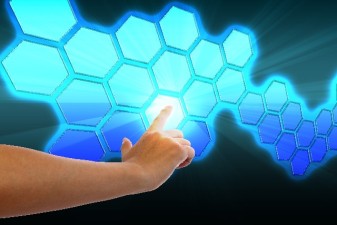
コメント