■ 揺れ動く各社のディスクロージャー姿勢‐決算短信の開示要件緩和の中で

前回、決算短信における業績予測の修正に関する実務の動きと、収益(売上高)の増減予測に総資産の増減および総資産回転率の変化がどう絡んでいるかの説明を長々としてしまいました。CVP分析がベースとしている「線形モデル」としての「短期利益モデル」の本質をご説明しようと、力が入りすぎ、丸々一回分の説明(投稿)が、CVP分析の連載にもかかわらず、一切CVP分析に触れずに終わるという失態。今回は、満を持してCVP分析の中身に触れていきたいと思います。m(_ _ )m
本題に入る前に、これまでの説明の概略を示すと、
(1)決算短信ではかつて経営者による業績予測とその修正が義務付けられていた
(2)昨今の開示業務の簡略化の流れで、業績予測とその修正は任意項目となった
(3)ただし、業績予測については、推奨のテンプレートが提示されている
(4)業績予測の修正公表については閾値と判断基準が定量的に示されている
● 業績予測開示項目
① 売上高
② 営業利益
③ 経常利益
④ 親会社株主に帰属する当期純利益
⑤ 1株当たり(当社株主に帰属する)当期純利益
● 業績予測の修正報告の基準(閾値)
① 売上高±10%の増減
② 経常利益±30%の増減
③ 当期純利益±30%の増減
④ 純資産または資本金±2.5~5%の増減
(参考)
● 決算短信・四半期決算短信作成要領等(2017年2月版)(PDF)
この、売上高±10%と、利益±30%が定量的に示されている根拠が、会計慣行の中で培われてきた財務分析データの蓄積と、それをベースにしたCVP分析による「短期利益モデル」の存在なのです。
■ 実証的な態度はとても大事! 会計慣行のホントが腑に落ちない場合は、自分で確かめればいい!
前回、売上高と総資産の増減の相関関係、その中で「総資産回転率」がどのように変化していったか、実証的な態度で、統計数値を用いて考察を重ねました。今回も、同じく、法人企業統計の最新過去10年のデータから、製造業の売上高と利益指標の推移を見ていくことにしましょう。
まずは、2005~14年における全製造業の売上高・利益・売上高利益率の推移グラフを作成します。

こうした財務指標に興味を持たれた方は筆者作の財務分析テンプレート紹介ページへ。
⇒「財務分析テンプレート『9 Matrix Financial Analytics』(無償版)取扱説明とダウンロード」
年次推移を追っていくと、2009年にリーマンショック後の需要蒸発の影響で売上高が最も落ち込んでいることが分かります。ここがトレンドデータ分析の妙というか面白さなのですが、売上高が底を打つ2009年の前年、2008年に経常利益、当期純利益ともに最低を記録している点です。この論点はまたまた本筋から離れるのですが、ついでに説明しておきます。2009年の売上減少とそれに伴う損失計上の発生規模が一定程度以上に大きく評価されると同時に、発生確率が非常に高いと見込まれたため、各種引当金が一斉に計上されたことが要因です。そのため、前回掲載した売上高・総資産の経年グラフにおいても、総資産が底を打つのは2009年ではなくて前年の2008年です。
しかしながら、経年トレンドを追う時系列分析は、データが連続して変化することを前提とする「連続変化モデル」におけるデータ解析手法です。今回は、統計確率的に売上高と利益額の増減の相関関係を知りたいため、「離散変化モデル」としてこの10年間の売上高と利益に迫りたいと思います。
そのために、次は時系列ではなく、売上高の増加に沿った連続データに並び替えて表示してみます。そうすると、年次ごとにバラツキが大きいですが、線形で近似値を求めた際に、経常利益率も当期純利益率も右肩上がりの直線を引くことができます。つまり、売上高が増えるごとに、一定割合で経常利益率も当期純利益率も上昇するという正の相関が認められるのです。これにより、売上高が増加(減少)すると、経常利益・当期純利益も増加(減少)することが分かりました。
前回に引き続き、しつこいですが、
① 本格的な統計学的な見地からは、有意性があるかどうか、もう少し厳密な定義が必要である
② 相関関係と因果関係とは異なる(一方がもう一方に影響を与えていることが分かるかどうか)
という留意点があることを念押ししておきます。①については専門家に任せるとして、②については、インベストメント・チェーンという財務会計的なモデルにより、因果関係があると(直観的な)ビジネスロジックで理解しても差し支えないと考えます。
● インベストメント・チェーン理論
① 資金調達 ⇒ 資本投下 ⇒ 収益(売上)獲得 ⇒ 利益の回収 (⇒再投資)
② 総資産 ⇒ 総資産回転率 ⇒ 売上高 ⇒ 売上高利益率 ⇒ 利益額
つまり、『決算短信』における「業績予想の修正」にて、売上高の増減も投資家の業績予想判断に資する情報で、その変化率がある一定程度に至れば公開することが有益であるということができます。投資家にとっての業績はつまるところ、どれだけ儲かったか=“利益”なので、“利益”増減の理由になりそうな“売上高”の増減もまた将来業績予測のために知りたくなるのは当然であることを数学的にも証明することができました。
ただし、上記の分析はあくまで確率論的に「離散変化モデル」として、売上高が増えると、利益額が増えることを説明したものです。決算短信における業績予想の修正が、前年度実績からの乖離幅だけに起因するものであるとするなら、それは「連続変化モデル」(いわゆる時系列モデル)でも、売上高が増えたら(減ったら)利益額も増える(減る)ことを証明しないといけません。それゆえ、閾値の設定は、前年実績対比のものと、前回業績予測対比のものの2つに対して設定されなければならないのです。
■ だから、どうして「±10%」と「±30%」の組み合わせなんだ? その理由が知りたいのに。
はいはい、理屈はもう十分でしょう。どうして売上高が「±10%」振れると、それが業績予想の修正として開示されることが要請されているのか。それは、売上高が「±10%」振れると、利益額が「±30%」増減すること(またはその逆)が長い会計慣行の中で経験則として知られている、と一般には理解されているからです。

当局(ここでは東証)が想定する売上高と利益の関係モデルは、売上高±10%振れると、確かに利益額が±30%増減することです。これは、上表の「当局が想定する売上-利益モデル」で示してあります。法人企業統計から10年間の総平均「経常利益率:4.3%」「当期純利益率:2.1%」を当てはめると、売上高が10%増加、かつ各利益が30%増加すると仮定した場合、経常利益率が0.8 point 改善、当期純利益率が0.4 point改善することになります。
これを弾力値(弾力係数、弾力性)で表現すると、弾力値とは、経常利益・当期純利益の変化率に対する売上高の変化率の比になります。筆者のような完全文系人間でもわかるように言うと、各利益の増分と売上高の増分の比率。
経常利益・当期純利益の売上高に対する弾力性 = Δ各利益 ÷ Δ総資産
※ 数学的には厳密性に欠ける数式ですが、理解のためにはこれで十分。
求められた「弾力値」は、それぞれ「3.00」(Δ30% ÷ Δ10% より)となります。
一方で、過去10年の法人企業統計から求めた同値は、
経常利益の売上高に対する弾力値:6.83
当期純利益の売上高に対する弾力値:23.72
前回試算した総資産の売上高に対する弾力値とは異なり、こちらは実測データと測定データとでかなりの乖離があり、サンプル数の少なさとリーマンショック前後というタイミングを考慮しても、ほぼ「当局が想定する売上-利益モデル」は破綻していると言わざるを得ないでしょう。
このことが意味することは、
① 会計慣行から導かれた、売上高±10%変動⇔利益±30%とは異なる弾力性が観察された
② そもそも、売上高増減とは異なる要因で利益増減がもたらされている可能性が高い
①について
従来の想定だった弾力値:3.00は、その昔、直接材料費と直接労務費が中心で、製造間接費が僅少だった時代の製造業のCVP分析の観察結果から求められたものです。昨今では製造間接費(いわゆるそのほとんどが固定費にも括られる)が製造原価の大半を占めるようになり、販売及び一般管理費における固定費比率も増加の一途をたどっています。したがって、いわゆる「固定費のレバレッジ」効果がより強まり、従来は、利益変動±30%をもたらす売上高の増減は±10%程度だったものが、同じ±10%の売上変動でその倍の利益変動をもたらす結果が法人企業統計によるデータ解析から求められたということです。

(参考)
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(4)チャートモデルを味わい尽くす - ビジネスモデル分析や利益モデリングを試みる!」
②について
例えば、2013年・2014年の利益増は、売上高増加に比して大幅なものになっています。これは、為替変動(円安)の影響が強く反映されている結果です。すなわち、利益増減の理由として、売上高増減だけを説明変数とすることが難しい経済状況になったということです。
■ 最後の最後に、CVP分析からチャート法での売上-利益モデルの破綻を説明します
ようやく、結論に言及することができます。

つまるところ、線形モデルである「CVP分析」に基づく「売上-利益モデル」では、例えば、売上高が10%増加すると同時に利益が30%増加するポイントは、たった1つの観測点でしか発生しないことから、シンプルで分かりやすいはずのモデルですが、経営状況を説明するモデルとしては荷が重くなったということです。

上図では、初期値を変動費比率:18%、固定費:1,000の場合、売上高+10%と利益+30%を実現する観測点は、売上高が1,833→2,017に増加する時だけです。この利益モデルは、「線形モデル」として作成されましたが、その実、たった一つの条件下でしか実現しないモデルであるため、率直に申し上げて欠陥品と言わざるを得ません。
その逆方向の説明として、売上高が1,833→2,017に増加する観測点に置いて、費用発生条件を、変動費比率:60%、固定費:489とした場合でも売上高+10%と利益+30%を同時実現することができます。
したがって、従来の会計慣行にて、たったひとつの線形モデルである「CVP分析モデル」から利益と売上高の変動を読むことで、売上高±10%と利益±30%が常に成り立つ(=恒等式)ことを証明することはできません。
たったこれだけのことが言いたいだけで、前後編約1万字の投稿を書き上げましたが、筆者のメッセージはどれくらい咀嚼してもらえたでしょうか。財務分析(入門編)のシリーズにしては、難解でしたでしょうか? (^^;)
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(1)イントロダクション - CVP短期利益計画モデル活用の前提条件について」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(2)基本モデルを理解する - 数式モデルの成り立ちについて」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(3)基本モデルを理解する - チャートモデルで可視化 」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(4)チャートモデルを味わい尽くす - ビジネスモデル分析や利益モデリングを試みる!」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(5)変動費型モデルと固定費型モデルの違い - 決算短信における業績予想の修正のカラクリ」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(6)決算短信の業績予想修正の根拠を探る旅①まずは法人企業統計と収穫逓増から」



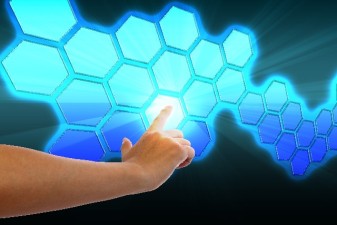
コメント