■ 原価計算の憲法は、「原価計算基準」です!
いよいよ、満を持して「原価計算(入門編)」のスタートです。
このシリーズでは、超入門から初めて、原価計算制度、原価管理方法まで解説を進めていきたいと思います。
さて、どの学問分野にも、お手本となる基本的考え方が示されている「法則」や「基本ルール」が存在していると思います。「公法」分野を学ぶ人は、まず「日本国憲法」を読まずして、その学習を前に進めることはできないでしょう。「原価計算」においても、憲法に該当する「原価計算基準」なるものが存在しています。
「日本国憲法」は、昭和22年に制定され、現時点(平成27年)まで、68年間もの間、改憲されていません。憲法改正の手続きが大変な硬性憲法であるがゆえ、先日、国際情勢の変化に対応すべく、集団的自衛権関連の解釈改憲(と、ここでは表現させておいてください)がなされました。「原価計算基準」も、製造業を中心とした、日本企業のものづくりの態様、原価を取り巻く会計基準の変化があれども、昭和37年に公表されたのち、53年間、一度も改訂されることなく、今日まで生き長らえてきました。
憲法同様、使えない、古くなったと批判する人もいるのですが、それなりに体系化されており、原価計算を学ぶ人、実務で使う人にとっては、その学習は避けて通れないものです。このシリーズも、基本的に、「原価計算基準」の世界観に従って、原価計算の世界に旅立とうと思います。そして、旅先のちょっとした分岐点で、最新の学説や実務解をご紹介していきたいと思います。
![]()
■ 原価計算の世界観 - 製品1個当たりの単価を求めるのがゴール
原価計算の目的にはいろいろあるのですが、とりあえず広い意味での「会計」の一分野でありますので、財務諸表にどのように関連していくのかを、まず理解しておく必要があります。下記のチャートをご覧ください。

原価計算で、製品(やサービス)の原価を求めることができれば、「損益計算書」に計上すべき「売上原価」と「販売費」が分かり、「営業利益」を計算することができます。と同時に、「貸借対照表」に計上すべき「棚卸資産」の額も明らかにしてくれます。この時の原価が持つ意味とはいったいなんでしょうか?
それは、「費用収益対応の原則」から、今期の売上(収益)に対応する費用の額を明らかにして、適正に期間損益を計算してくれるところにあります。そして、この費用収益の対応のさせ方には、大別して2つの方法があります。
(1)1個2個と数えられ、販売される製品・サービスの単位当りコスト
(2)その期に販売された製品・サービスの販売努力に差し向けた時間にかかったコスト
例えば、トヨタ自動車が、1年間に100万台の乗用車を製造・販売するとしましょう。販売される自動車一台当たり、使用した材料費、工場で働く人に払った給料(労務費)、工場の建屋や使用する生産設備の減価償却費や、工場の運営にかかる水道光熱費など(経費)は、1台当たりの原価単価を求めて、売れた台数分だけ、「売上原価」に計上します。
一方で、その100万台を売りさばいたセールスマンへ支払う給料や交通費は、販売された車の一台一台に、それぞれいくら、とカウントすることができないため、100万台売れた会計期間(例えば1年間)全体で、セールスマンに支払った金額を認識して、100万台売るために会社が犠牲にした期間費用(言い換えれば、セールスマンに支払った給料や立て替え精算交通費)を「販売費」として総額で計上します。
![]() このことを、今度は、上記のチャートの左からの流れに従って、再説明してみます。世の中一般に、「原価」「費用」「コスト」の名前で呼ばれている概念が、ちょっとずつ変化しながら、財務諸表までたどり着く、旅路を理解できるはずです。
このことを、今度は、上記のチャートの左からの流れに従って、再説明してみます。世の中一般に、「原価」「費用」「コスト」の名前で呼ばれている概念が、ちょっとずつ変化しながら、財務諸表までたどり着く、旅路を理解できるはずです。
まず、会社は、損益計算するために、その会計期間に発生した費用をすべて集計します。それが、「発生費用」と呼ばれるもので、「材料費」「労務費」「経費」「販売費」の全てを含む、一番広い概念です。
次に、「発生費用」を、製品・サービスの単位ごとに集計したい「製造原価」と会計期間でしか識別できない「販売費」とに分けます。
「製造原価」は、集計された金額を、完成した製品の数で割ることで、製品単位当たりの原価として求まります。この製品単位当たりの、いわゆる「原価」と呼ばれる「単価」が、広く一般に、「原価」「コスト」として認識されているものになります。
最後に、「製造原価」(もしくは、それを生産台数で割った、製品単位当たりの製造原価=製造単価)のうち、販売されて、損益計算書上、売上原価として計上すべき金額を、販売数量から計算します。この、「販売数量×原価単価=売上原価」という計算式で、「売上原価」を算出する元ネタとしての、「製造原価」(もしくは製造単価)を求める部分が、原価計算手続きです。
ここで補足しておくと、売れ残りは、その製造単価×数量分だけ、在庫として、貸借対照表の棚卸資産として、流動資産扱いになります。そして、来年、それが売れれば、今度は、棚卸資産から、売上原価に、売れた台数分だけ振り返られます。
世の中一般的には、「売上総利益」の上に来る「売上原価」の元ネタになる「製造原価」を求めるところが、「原価計算手続き」と理解されていますが、原価計算世界の憲法であるところの、「原価計算基準」においては、「販管費」まで含めて「原価計算手続き」としています。したがって、「原価計算基準」の世界観では、「営業利益」を計算するのに必要なコスト集計をするのが「原価計算手続き」である、という立場をとります。
まあ、販売費や一般管理費は、「期間対応」と言って、会計期間に発生した分を損益計算書に計上すれば済む話なので、製品単位当たりの、いわゆる単価を求める必要はないので、それほど計算ロジックが複雑にはなりません。しいて言えば、経過勘定(未払いや前払いなど)の処理にだけ、留意しておけば、あまり問題は無いでしょう。したがって、ちょっと構えて、「原価計算」とは? と語り出す際は、おおむね、「製品原価」を求めるところが複雑で、またいろいろ計算処理に選択肢があり、どれにするか迷いが生じる、ということになります。
でも、ゴールから考えれば、目的は明確ですよね。
『製品単位当たりの製品原価(製品単価)を求める』
![]()
■ 製品原価計算のステップ
それでは、製品(またはサービス)のひとつひとつ、いわゆる製品単価を求める計算手続きについて、これまた「原価計算基準」に則って、説明したいと思います。下記チャートをご覧ください。

<1ステップ:費目別計算>
まず、製品単価を計算するために、製品ごとに集計したい費用を全社から集めてきます。これを「費目別計算」といいます。一部例外があるのですが、ここでのポイントは、「製品原価」に組み入れたい費用と、「販売費」などの、「期間原価(費用)」と、費目(勘定科目)で分けられる場合は、このタイミングで「期間原価」は取り分けておくことです。
<2ステップ:部門別計算>
つぎに、前ステップで集計されてきた製造原価の元を、単価計算できる「かたまり」に再集計していきます。上図にあるように、製品単価を計算する「かたまり」を、生産工場にある「A製造ライン」と「B製造ライン」の2つとします。2つのラインは、1つの工場内にあります。工場全体の品質管理や、機械の保全・修理を担当している部署で発生しているコストを、ここでは便宜的に、「補助部門」(=直接製品を作っていない部門)で発生した「経費」と呼んでおきます。この「経費」は、「補助部門」で「100」だけ発生したことが分かっているのですが、「A製造ライン」と「B製造ライン」のそれぞれでいくら発生したのか(負担すべきなのか)、明らかにするのはちょっと困難です。
そこで、この「100」をある配分ルールで「A製造ライン」と「B製造ライン」に、それぞれ「60」と「40」に分配しておきます。ちなみに、この分配ルールが原価計算を論じるときの大事な論点になりますので、以後の投稿で必ず詳細を説明することをここにお約束しておきます。
また、「材料費」と「労務費」は、直接、倉庫から払い出す際の記録簿、または工場勤務者の勤怠表から、それぞれのライン(部門)にいくらずつ割り当たるか分かっているので、そのまま記録簿を信頼しておきます。
ちなみに、ここでも、補助部門のみならず、全部門にわたって、費用の内容を調査して、「製造原価」にしていいものと、「期間原価」にしていいものの識別をもう一回しておく必要があります。この2ステップ目で、「期間原価」にすべきものが発見されたら、その該当額分だけ、「製品原価」を計算する元ネタから差し引いておきます。
<3ステップ:製品別計算>
最後に、製品原価を計算する「かたまり」、上図では、「製造ラインA」と「製造ラインB」の2つですが、それぞれに集計された「製造原価」を、各ラインで生産された製品数量で割り算してあげて、製品単価(製品1単位当たりの製造原価)を算出します。
こうして、原価計算手続きのゴールである「製品1単位当たりの製品原価(すなわち製品単価)」が求まりました。あとは、売れた分は「売上原価」へ、売れ残った分は「期末棚卸資産」へ、それぞれ振り分ければ、損益計算書と貸借対照表へ、原価計算の結果が表示されることになります。







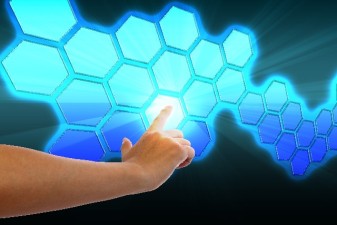
コメント