■ 原価計算基準の体系について

ここから、原価計算基準の「第二章 実際原価の計算」が始まります。細かいことですが、どうして「実際原価計算」と呼称せずに、「実際原価の計算」と接続助詞の「の」を入れたのか。原価計算の本質を学習したい人には余計な情報かもしれませんが、原価計算基準の体系を理解したい人にはちょっと耳をお借りさせて頂きたいポイントです。
下図が原価計算基準の体系となります。

第三章では「標準原価の計算」が取り上げられています。これも「標準原価計算」という呼称になっていません。この些細に見えるが筆者が拘るワーディングには意味があります。原価計算基準は原価計制度として、①実際原価計算制度、②標準原価計算制度の2つを想定しています。原価計算基準の第二章で「実際原価計算制度」を説明した後、第三章で「標準原価計算制度」を改めて説明しようとすると、第二章で既に解説済みの説明が重複してしまいます。なぜなら、標準原価計算が行われるということは、その前に必ず実際原価計算が行われていることが前提条件になっているからです。
「第三章 標準原価の計算」では、標準原価の計算に特化した説明になっており、その前提となる実際原価の計算と共通事項である費目別計算、部門別計算、製品別計算の手続きなどは省略されています。

その後の「第四章 原価差異の算定および分析」「第五章 原価差異の会計処理」の内容は、再び実際原価計算制度と標準原価計算制度の両方に関する記述がまとめられているのです。
■ 製造原価と販売費および一般管理費の計算プロセスの違い
第二章 実際原価の計算
七 実際原価の計算手続
実際原価の計算においては、製造原価は、原則として、その実際発生額を、まず費目別に計算し、次いで原価部門別に計算し、最後に製品別に集計する。販売費および一般管理費は、原則として、一定期間における実際発生額を、費目別に計算する。

● 製造原価について
部門別計算において、材料費20をすべて購買部門へ、労務費は25を製造部門へ、5を補助部門へ、経費は40を製造部門と補助部門へ等分で割り当てています。製品別計算において、生産在高が10個なので、総製造費用90を生産在高で割り算することで製品1個当たりの原価を算出しています。その内、7個が販売されて売上原価へ、3個が売れ残りで期末在庫へ振り替えられます。
● 販管費について
原価計算基準においては、費目別計算にて、どういった内訳科目で費用が発生したかを明確に把握した後、「費用収益対応の原則」の考え方により、そのまま実際発生額の全てが期間費用としてP/Lに計上されます。
製造原価と販管費において、上記のような差別的取り扱いになるには理由があります。原価計算基準における「原則として」販管費を費目別計算に留め置くのは、
① 財務諸表作成目的
原価計算基準は実践規範であるため、絶対的強制力(法的拘束力)はありませんが、ある程度、どの業種でも、どういった企業規模でも共通的な適用が要請されます。そこで、あえて中小企業に過度な負担にならないように、販管費の部門別計算プロセスを「原則なし」としているのです。販管費の製品別計算プロセスは、販管費が棚卸計算対象費目ではないので、当然として対象外となります。
② 原価管理目的/予算管理目的
会計実務において、販管費を部門別に把握することはよくあることです。その目的は、販管費の支出コントロールするために、部門長に対して費用管理の会計責任を設定して、コストセンターとしての発生費用の予算統制を行うための単位とするためです。
また、セグメント別業績管理(収益性分析)のために、特定のセグメントにも販管費を紐づけるための橋渡しとして、部門を用いる際にも、販管費の部門別計算が行われることがあります。
これらは、「原価計算基準」で規定されているから実施されるのではなく、原価管理、予算管理、業績評価や収益性分析といった、管理会計の諸目的に対応した各社の自発的な要請によるものです。
■ 製造原価と販売費を会計実務として区別する方法は2つ
前章までが、いわゆる「原価計算基準」にある規定の逐条解説になります。それでは、そもそも、会計実務では製造原価と販管費とをどうやって明確に区別しているのでしょうか。筆者の知る限り、大別して2つの方法があります。
前章の「原価計算ステップから財務諸表作成まで」は、わざと、無理がある勘定科目の識別方法を採っています。
① 製造原価に分類されている「労務費」と、販管費に分類されている「人件費」は、支出内容および、金額の把握方法はひとつなのに、どうやって「労務費」と「人件費」に分けることができるのか?
② 同じ科目名で発生金額が把握された「経費」をどうやって「製造原価」と「販管費」とに明確に区分することができるのか?
ひとつは、費目別計算ステップの中で処理する方法、もうひとつは、部門別計算ステップまで進んで処理する方法が考えられます。
(1)勘定科目識別法
発生の源泉が似たもの同士、製造原価に括られる科目と、販管費に括られる科目と、科目名で印をつけて区別する方法です。伝票から分ける方法、伝票を仕訳帳に記載する際に分ける方法、総勘定元帳にて識別する方法など、各社の会計情報の作成プロセスのどこかの時点で、勘定科目だけで「製造原価」か「販管費」かの区別がつくようにします。

(2)部門振替法
費用が発生した際には、製造原価と販管費と共通の勘定科目でいったん計上します。その際に、どの部門で発生した費目なのかを明確にしておきます。製造部門で発生した費用ならば、計上の後に、製造原価へ振り替えます。この時、各社の勘定科目体系の考え方次第ですが、一括して「製造原価(総発生費用)」という勘定科目に振り替えるか、その内訳として、「材料費」「労務費」「製造経費」という明細情報を持ったまま振り替えるかは、管理の手間と目的次第と考えます。

■ 管理会計にとって使える方法はどっち?
会計実務家にとって、制度会計と管理会計の整合性はいつの時代でも重要なテーマです。原価計算基準は、原価計算制度を前提に考えられており、原価計算制度は、管理会計目的も満たしつつ、一方で財務報告機構との有機的結合によりデータの正確性・首尾一貫性を担保するも目指しています。
ここは、各社の財務会計機構の設計構造によるところが大なのですが、筆者の好みと使い勝手のよさから、「部門振替法」をひとまずはお勧めします。
① 発生費目の一元的管理が可能
例えば、「人(労働力)」という経営資源を調達するために費やされた金額が、全社規模でかつ特定の会計期間で区切った所で「人件費」という費目だけを見れば一目瞭然である、という状態は分かりやすいと考えています。分かりやすいは効果的な管理の第一歩です。
② コストセンターとしての会計責任が明確になる
全社で発生するコストは、記帳する段階で既に誰か(どこかの部門)の発生責任を問えるような会計データ構造になっていることは、会計責任を徹底するための前提条件です。ある経費はそれぞれの部門で使ったことが分かるけど、例えば材料費や水道光熱費が、全社部門というダミー部門コードでしか把握されていないとしたら、、、それぞれの費目が特定の人・部門でしか発生しないという特殊事情が無い限り、誰の、どこの責任かは曖昧になってしまいます。
ご参考にしてください。
⇒「原価計算基準(1)原価計算の一般基準の体系を整理 - ざっと原価計算基準の世界観を概括してみる!」
⇒「原価計算 超入門(2)実際原価と標準原価」
⇒「原価計算 超入門(5)基本的な原価計算の流れ -製品原価を求めてみる」
⇒「原価計算基準」(全文参照できます)



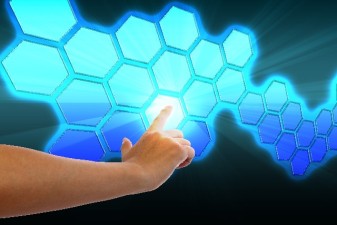
コメント