■ 管理会計(入門編)として「財務分析」が始まります

「管理会計(基礎編)」で、ベーシックな管理会計の考え方を浅くですが、一通り説明しました。「入門編」は、分野ごとにテーマを決めて解説を進めていきたいと思います。このシリーズは「財務分析」を扱っていきます。
「財務分析」とは(あまりこういった大上段に構えた定義は好みではないのですが)、
「主に『財務諸表』の数字を中心に、時には、人員数や面積、生産高、数量、金利、時間などの計数情報も駆使して、『数字』で企業の経営実態を把握すること」と、筆者は考えています。
ものの本には、計数の分析アプローチから、「実数分析」「比率分析」「構成比分析」「趨勢分析」などという分類をしていたり、「比率分析」で分析対象とする指標群を、「収益性指標」「効率性指標」「安全性指標」などという分類をしていたりします。
また、立派な「分析シナリオ」「企業分析メソッド」というものがあって、数字(特に貨幣価値‐金額)で定量的な表現をする「財務分析」はそれらの方法論の一部に取り込まれていたりします。
このシリーズでは、そういった「分類方法」や、「経営分析手法」も、参考情報として解説はしますが、特定の分析手法に偏りもせず、かといって筆者独自の分析手法をひけらかすこともしません。淡々と、財務分析の個々の手法を説明していきます。
■ とはいうものの、一応の枠組みは示しておきます
あくまで、筆者の説明の全体像を把握してもらうために、全体のフレームワークは仮設定として最初にお示しします。読者の方が、株式投資や企業経営、はたまた経営コンサルティングにて、財務分析に関する知恵が必要になった時には、筆者のフレームワークで整理した各財務指標を、ご自身の使いやすいように使いこなしてみてください。
というのは、ブログへの記事投稿が、「基礎編」と違って、必ずしも先頭から順を追って行う予定ではないので、筆者の仮フレームワークは頭の片隅にでも置いて頂いておかないと、筆者がどこの財務分析の話をしているか、分かりにくくなるからです。つまらないフレームワークかもしれませんが、ひとつの整理法としてご活用頂ければ幸いです。
では、まず、財務分析したい企業の経営モデルの仮説をご紹介します。

1.企業が直面する外部環境(タテ)
経営資源は、「ヒト」「モノ」「カネ」(最近は+「情報」)と分類されることが多いですが、このフレームワークでは、金融市場から調達してきた「カネ」を元手に、「モノ」「ヒト」を実物市場で調達するという形で、企業は2つの市場と対面することを前提にしています。
2.ビジネスの因果関係(ヨコ)
企業経営は、まずリスクをとって事業に投資をして、うまくいけば投下資本からリターン(儲け)を手に入れることでひと続きの事業が完結すると考えることができます。
3.ゴーイングコンサーン(継続企業)の前提
金融市場から調達してきた資金を事業に投資した結果、得られた果実から、資金の出し手に儲けを分配して終わりにするのはもったいない、得られた果実を次の新規事業、または来月の継続事業に再投資してもっと儲けようと考える人も出てきます。そうすると、企業は、キャッシュを生み続けるキャッシュ・マシーンになぞらえることができます。
この半永久的なサイクルを示したのが、上図の①から④までのサイクルになります。
■ 経営サイクルの各フェーズに対応して財務分析を行う
筆者の仮説としての、経営サイクルをご理解していただきましたら、今度はこの図に、分析対象としたい「財務指標」または「財務分析手法」をマッピングしてみたいと思います。

①資金調達から②事業投資へ
ここでは、「資金分析」を行います。せっかく資本家から集めた虎の子の資金を経営者が適切に事業に投資しているか、投資実態に無理がないか、資金がショートして倒産の危機に陥っていないか、をチェックします。
この辺は、そもそも「財務分析」が、銀行家が経営者の資金運用に対して、「信用調査」するところが発祥となって発展してきているので、保守的な人種(?)である銀行家を安心させるための分析手法になっています。
(現在の財務比率分析はここから誕生したという説が有力です)
②事業投資から③投資回収へ
ここは、事業家(経営者)の腕の見せ所です。経営者の先見の明で先行投資した事業がどれくらい儲けることができたのか、を明らかにします。その際、利益率の高さ(儲かり度具合い)を測るのですが、投下した資本に対するリターンということで、「ROI:Return on Investment」を見ることが基本形です。ROIは、間に売上高を挟むことで、売上高に対するマージン率と、売上を生み出す事業投資の事業創造性とに分割することができます。
前者がここでいうところの「収益性分析」、後者が「効率性分析」というアプローチで明らかにされます。
③投資回収から④資金配分へ
ここでは、事業から得られた儲けをステークホルダーにどういう判断基準で分配するかに関心が生まれます。一枚の「パイ」をどのように切り分けるか、厚生経済学のように、「公正」とは申しませんが、「適切」に利益を分配したいものです。
ここでいう「適切」というのは、ゴーイングコンサーンとして、事業再投資、事業の半永久的な成長を可能にする分配をする、という意味です。ただですね、必ずしもひとつの経営体にこだわることもありません。投資家が資金を預ける器としての企業を乗り換えたければ、その乗換方法や代替資金の用立て方法もここで議論できるような分析を行います。
④資金配分から①資金調達へ
ここでは、主に、投資家(将来の株主や債権者)が企業体への投資の適切性を評価するための計数分析を行います。いくら投資したら、いつの時点でどれくらいのリターンが見込めるか、そのリスクとボラティリティとリスク許容度はどれくらいか、といった評価を行います。
■ 収益性の裏表関係に気づきました?
世の中で、一般的に「収益性分析」といったら、「いくら投資したらいくら儲かるか」、素直に考えればその字句通りです。しかし、上図では、投資とリターンの関係性から導かれる「収益性」は上下で2回登場します。
投資家が、企業に(再)投資の判断する際の「投資収益性」の評価と、
経営者が、事業に(再)投資の判断をする際の「事業収益性」の評価です。
この収益性の二重性は、貸借対照表(B/S)を挟んで、左に経営者、右に投資家を配置すると、複式簿記(会計)的にも理解が進みます。

投資家は、投資利回りを気にします。株主目線ですと、その投資利回りが、単なるインカムゲイン(配当金)だけなのか、キャピタルゲイン(自己株式取得をふくむ株価上昇)も含むTSR的なものなのか、という違いは場合により違いがあります。また、時価ベース(株式利回り・配当利回り)なのか、簿価ベース(ROE)なのか、ということも気になるところです。
さらに、EP、残余利益、経済的付加価値などの指標を問題視するかもしれません。しかし、それらは、結局のところ、投資家の手に入らなければ意味がありません。経済的付加価値自体は、投資家の手元に、リアルキャッシュの形でそのまま届くわけではありません。そういう収益性評価をした結果、株式の売買の形(キャピタルゲイン)またはそれを基にした信用取引の形でようやく果実が投資家のものになります。
ここが、企業価値評価系の指標とROA・ROE・ROS等のいわゆる「R系」の指標との違いになります。
(この論点は、ある読者の方には唐突すぎて難しいかもしれません。追い追い説明しています。ここでは、2種類の立場によって異なる収益性指標があるとだけご認識ください)
■ 今回のオオトリ - 財務分析体系と代表的指標の例示
それでは、筆者の仮フレームワークで整理された「財務分析」体系と、各分析箇所での代表的な指標をマッピングした図をご紹介します。

左側中央の、「資金分析」は、「CF(キャッシュフロー)分析」と「安全性分析」にさらに分類しています。あくまで、筆者が便宜的に分けているので、ものの本では、いささか命名が異なるかもしれません。
右側は、「財務分析」する際に、最も皆さんが興味があるだろうと思われる「収益性分析」がさらに、下位4つに細分化されています。
「成長性分析」は、儲け(利益)そのものの増分分析もしますが、利益のもととなる売上の成長も分析対象とします。もっというと、売上のもととなる、人員や資産の増え方とのバランスまで見ることになります。
「生産性分析」は、単位あたりの収益性(売上だったり利益だったり)を見るものです。指標の組み合わせ方によっては、「付加価値分析」と組み合わされたりします。ですので、こうした分類はあくまで便宜的に、と申し上げています。
「CVP分析」は、外部公表用の財務諸表からは扱えないこと、線形分析が経営実務にあっていないのではないかという批評が最近あること、等から、取り扱いには要注意な指標となります。筆者の経験からは、企業内部情報にアクセスできる場合には、まだまだ有効な指標を提供してくれると考えています。
ここまで、「財務分析のフレームワーク(1)」を説明しました。



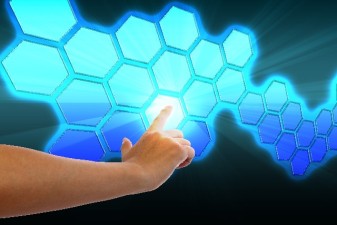
コメント