今の問題の過去履歴にも着目する
このシリーズは、G.W.ワインバーグ著『コンサルタントの秘密 - 技術アドバイスの人間学』の中から、著者が実地で参考にしている法則・金言・原理を、私のつまらないコメントや経験談と共にご紹介するものです。
外部リンク G.W.ワインバーグ氏の公式ホームページ(英語)
前回、問題解決メカニズムの有無を確認した後の、コンサルタントの2つの問題解決アプローチのお話をしました。ポイントはクライアント自身が問題解決メカニズムを知っているか否かでした。そのためには、クライアントが抱える問題の分布に着目することから分析を始めていました。
関連記事 コンサルタントの秘密 – 技術アドバイスの人間学(40)問題解決の問題を解決する方法① - 解決方法の欠如
問題の分布そのものに目を向けるもの大切なことですが、さらにその分布が持っている歴史にも目を向けてみましょう。現在の問題の分布の様(さま)は、時間軸の経過とともに今の形と分布を形作っていると思われます。
現在の問題の分布をもたらせた歴史的な過去の事実の影響を推し量ることで、問題解決の糸口を見つけることができる可能性が高いからです。また、過去からの経緯は、時間軸に沿った物事の因果関係の連鎖そのものでもあります。「現在の問題を解決する = 現在の問題をもたらした過去の出来事との因果関係を切る」ことで、現在の問題を解決できるかもしれないのです。
問題の過去履歴が分かった時にどう対応するか
ワインバーグ氏はこのやり方に対する基本的態度を次のように説明しています。
もし圧倒的な大問題が最近になって、たとえば何らかの外的要因のために引き起こされたものであるのならば、その問題に直接対決し、それによって依頼主が今度の問題が持ち上がる前には持ち合わせていた問題解決メカニズムを活性化させる、というのがよい手であるかもしれない。
G.W.ワインバーグ著「コンサルタントの秘密―技術アドバイスの人間学」(P81)
ワインバーグ氏は本書の中で、キーマンが突然死んでしまった場合、組織はどう対応するべきか、といういささかショッキングな事例(本当の体験談とのことですが)を引いて説明しています。
もし、キーマンがどんな仕事をしているか、職務記述書(job description)が存在していたり、従前から有給取得をしてキーマン抜きの場合の仕事のこなし方について訓練・経験があったりする組織の場合、キーマンの部下から適任者を後任に充て、残ったスタッフと一緒にキーマンの仕事を分割してそれぞれに割り当てることで、キーマンが抜けた穴を埋めることができます。
もし、キーマンがどんな仕事をしているか、詳しい状況が不明な場合、上のような対策を講じることは物理的に不可能です。そういう場合は、その組織が機能不全になる、もっと悪い場合は組織が崩壊する、という恐怖心をテコにして、何か小さい構造的変化を組織に持ち込みます。
これは、前回、「問題解決方法が見つからない場合の対処」として説明したものに当てはまります。小さい変革から初めて、組織自身がどうやってキーマン不在に対処するか、自ら学び、自ら環境対応していくことをできるだけ効率的に進めることにコンサルタントが心砕くのです。
見えない仕事を見える仕事にする方法
なんでも一度モメンタム(勢い)が付けば、慣性の法則にしたがって、自走することができます。何でもないところから、ときにはマイナス方向に進んでいるものを、意図する方向に進めるには最初の一歩の働きかけに大層エネルギーを使ってしまうものです。
ここではコンサルタントの所作について語っているので、そうした変革の起点づくりについて、ワインバーグ氏が例示したものを使って丁寧に説明してみます。

キーマンが突然組織からいなくなり、かつキーマンの仕事内容が不明である場合、キーマンの仕事を雲(ブラックボックス)にして、その雲との間でやり取りをしていたAさん、Bさん、Cさん、Dさんとキーマンとの間でやり取りされていた情報・モノを洗い出します。その際に、可能な限り、やり取りのタイミングの前後関係も明らかにします。
他の関係者とキーマンとの間でやり取りされるもの、やり取りする方法 → インターフェース
他の関係者とキーマンとの間でやり取りされるタイミングのズレ → 作業プロセス
の2つが浮き上がります。
後は、この作業プロセスをマニュアルとして文書化するもよし、ITを活用して業務アプリケーションに仕立てるもよし、お好きな方法で、キーマンのお仕事を可視化・標準化・定着化してください。
関連記事 コンサルタントの秘密 – 技術アドバイスの人間学(39)平準化の法則 - たった一つの支配的課題だけを抱えない
関連記事 コンサルタントの秘密 – 技術アドバイスの人間学(42)問題解決の問題を解決する方法③ - 助力への要請の欠如
みなさんからご意見があれば是非伺いたいです。右サイドバーのお問い合わせ欄からメール頂けると幸いです。メールが面倒な方は、記事下のコメント欄(匿名可)からご意見頂けると嬉しいです。^^)


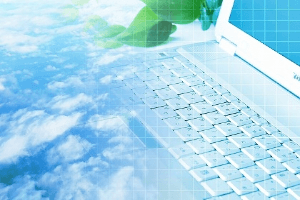
コメント