■ ビジネスモデルと変動費・固定費の関係

前回、「変動費中心のビジネスモデル」と「固定費中心のビジネスモデル」の2つがある、ということについて言及はしました。これは、様々な業種・業界、または特定の業種でも、その中での競争戦略次第では、個々の企業がどのようなコストのかけ方をするかで、変動費中心になるか、固定費中心になるか、費用の支出のされ方はその会社それぞれ。それゆえ、一刀両断に○○業界は変動費型ビジネスだと断定することはできません。
そして、管理会計がビジネスモデルを規定するのではなく、ビジネスモデルの方からどのように計数管理した方が良いか、管理会計に問いが出され、その問いに応える形で、固定費中心の管理か、変動費中心の管理か、相対的に有効なコストマネジメントの手法を管理会計は提供するだけなのです、という筆者のスタンスの一端を説明したつもりです。
一昔前は、労働集約的な企業は、変動費型ビジネスモデル、資本集約的な企業は、固定費型ビジネスモデル、と紋切型の分類がなされたものです。従業員というものは、ビジネスが軌道に乗り、規模が拡大したり、業態が複雑になれば、必要に応じて募集をかけて集めればよい。もしビジネスが下降基調になれば、レイオフしてコストオフすればよい。そのような労使環境の国では、確かに労働集約的な企業は変動費型といっても構わないでしょう。しかし、日本の従来の労使環境は、正社員はそんなに簡単に解雇できるのでしょうか。欧州もまたしかり。米国や日欧以外の国・地域でも一部は解雇が柔軟にできる場所ではその通りですが、少なくとも、従来型の日本企業において、労働集約産業 = 変動費型ビジネスモデル、という図式は成り立ちません。
また、製造業は、長期雇用を前提とした正社員が、経験曲線理論に基づき、習熟度を上げて、高品質かつローコストな製品を世に送り出す、という日本式ものづくりを実践している場合、どう考えても、原価構成に占める加工費(労務費)比率が高い製造業だからと言って、変動費型ビジネスとは決して言いきれないのです。逆に、正社員を抱える以上、その人件費は短期的に支出回避できないという意味でむしろ固定費と言わざるを得ません。
■ じゃあ、資本集約的な企業や流通業はどうなのか?
化学や鉄鋼等の素材系メーカーは、装置産業なので、資本集約的。その資本とは、機械や建物として有形固定資産の名で貸借対照表(B/S)に計上され、損益計算書(P/L)では、減価償却費としてコストに化けます。この減価償却費は、設備・工場を売却しない限り(そのビジネスをやめない限り)、発生を回避できないので、その意味で固定費と位置づけられます。しかし、資本集約的といわれる装置産業は本当に固定費型ビジネスを行っているのでしょうか。そういう素材系企業は、外部のサプライヤーから購入してくる材料費も相当な額に上ります。外部から調達する材料費はそれこそ、ビジネスの繁忙に合わせて、購入量が上下しますので、変動費とするのが妥当でしょう。それゆえ、装置産業 = 固定費型ビジネスモデル という図式も必ずしも成り立つとは限らないのです。
それでは、サプライヤーから仕入れた商品を売買している流通業は、業界をあげて、変動費型ビジネスモデルを採用していると言えるのでしょうか。実はそれも否です。小売業の規模トップにあるイオンのB/Sを眺めてみて下さい。
2016年2月決算において、
・棚卸資産(在庫):5756億円
・有形固定資産 :2兆6154億円
となっています。
巨大なショッピングモールに代表される数多ある商業施設。それらの減価償却費は全て固定費なのです。1903年に考案されたCVP分析。当時は、労働市場におけるルールもシンプルで、かつ、製造業においては熟練工より一時雇で出来高制の単能工による分業が主流。流通業においては、大量仕入れ、大量販売で販売施設に多額の投資は不要な時代でした。そういう古典的な産業観についての常識だけを引きずったまま象牙の塔に立てこもっている一部の会計学者が書く教科書で、○○業種は固定費型、△△業界は変動費型、と記述してあっても、まずは疑ってかかってみた方がよさそうです。
■ 決めつけるんじゃない、ファクトから感じるんだ!
じゃあ、CVP分析の対象企業の財務諸表を眺めて、変動費型か固定費型かじっくり観察してみよう、と思い立ち、決算短信や有価証券報告書など、外部公開資料を矯めつ眇めつ(ためつすがめつ)眺めてみても、またはホームページを漁ってみても、変動費と固定費を完全に仕分けることができる十分な情報は得られません。
その主な理由は、2つ考えられます。
(1)製造原価報告書(製造原価明細書)の開示義務が無くなった
(2)最小二乗法による固変分解の限界
(1)製造原価報告書(製造原価明細書)の開示義務が無くなった
金融庁は2014年3月に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公布し、ここで、財務報告者の作業負荷を考慮し、セグメント情報をきちんと開示していれば、製造原価明細書を損益計算書に添付しなくてもいいものとしました。その後、連結財務諸表規則が改正され、製造原価報告書(製造原価明細書)の文言は影も形もなくなってしまいました。それゆえ、企業外部の利害関係者が、自由に縦覧できる財務諸表から原価明細が外されたため、この明細を使い、いわゆる勘定科目の名称を使っての「固変分解」は企業内部の関係者しか実質的にできなくなってしまいました。
(2)最小二乗法による固変分解の限界
企業外部の利害関係者が使えるものは、四半期決算における損益計算書程度のもの。そのP/Lから、売上高と総原価(売上原価+販管費)の2つを取りだし、両者の相関から、統計的に「最小二乗法」という手法を使って「固変分解」を試みるのですが、有効な分析結果が得られることは稀になりました。なぜならば、流通・サービス業から製造業まで、固定費の比率がそこそこ高くなったとの同時に、企業内部で費用発生を回避可能な固定費の割合も増えてしまいました。これを筆者は特に、「裁量固定費」と呼んでいるのですが、これがあたかも「変動費」のように表出してくるのです。
企業は大抵、年度予算を策定します。年度末に向かって、期初に立てた利益目標値が未達になりそうな場合、目先の売上高とは直接連動しない、施策費(売上高と比例関係にないという意味で固定費になる)の予算執行を停止し、利益目標を達成しようと施策費(筆者の言う裁量固定費)を削ります。それゆえ、最小二乗法が割り出した計算結果が何とも奇妙な答えを出すようになるのです。

経営活動量(売上高で代替)がゼロの時、固定費がマイナス値となってしまうのです。筆者も、事業会社で経営企画部門にいた頃、自社や競合他社のCVP分析比較をやりたくて、その動機は、どこまで市場で値引きできるかを知りたいため、だったのですが、何度繰り返しExcelの計算式を見直してもマイナスになってしまうのです。
■ 奇跡的な有価証券報告書を偶然見つける!
企業財務分析を趣味と実益(仕事として、一個人投資家として)を兼ねて、20年以上続けてきましたが、奇跡的に、現時点でも製造原価明細書や傘下の個社財務諸表を開示してくださる貴重な企業が複数存在します。今回はその貴重な企業のひとつ、JFEホールディングスの有価証券報告書から、CVP分析を生身の数字で味わっていただきたいと思います。
まずは、JFEホールディングス傘下の商事(流通業)と、スチール(製造業)の総原価を固変分解した(段階利益としては営業利益まで)管理会計上のP/Lを表示します。通常、固変分解したP/Lは1年間の会計期で作成するものです。それは、短期利益計画が1年サイクルで策定されること、固定費が「固定」として発生不可避なコストである期間が1年であるとの仮定に基づく既成概念からくるものです。そうそうドラスティックに年単位で固定費の発生元である設備投資計画が大きく上下することは考えにくいので、こうした数年単位の固変分解でも十分に使用に耐えるものと考えます。
残念ながら、FY14は、商事の方の情報開示はありませんでした。JFEホールディングスは、ご存知の通り、NKKと川崎製鉄が合併した会社です。JFEスチールの開示数字も、連結と単体両方あり、その上でホールディングスの数字も連結として開示されています。幾重にも管理階層が存在し、社内で数字を管理している経理担当者の苦労がしのばれます。また、こうした階層の数字が部分的にも開示されているのは、合併会社ならではの経緯があってこそと推察しています。


さてさて、数字を眺めてみると、JFE商事の方は販売子会社として、固定費がほぼ存在していません。一方で、JFEスチールの方は、ものづくりをしているので生産設備に起因する固定費が存在します(それでも、鉄鉱石や石炭などの原材料の購入高が相当の比率になっていますが)。数字だけご覧いただき、両社のコスト発生状況と利益の上がり方に癖があるはお気づきでしょうか。両社の違いは、グラフ化するともっと違いが際立つはずです。
いつもながら、数字を並べただけでは、頭に染み込んでこないので、可視化するために積上げグラフでも表現してみます。数表とグラフを何度か見比べてください。固定費がほぼ存在しない、JFE商事の方は、限界利益と営業利益の変動するトレンドと変動幅がほぼ同期し、かつ狭い範囲でしか動きがありません。一方で、固定費比率が4期平均で約25%あるJFEスチールの方は、ちょっとした売上の増減で、営業利益の変動幅が大きく増幅して動いていることが分かると思います。つまり、固定費があった方が、ちょっとした売上の増減で、営業利益が大きく振れることを意味しています。


これは、固定費のレバレッジ効果といって、固定費があるビジネスの特徴になります。損益分岐点は高くなってしまい、量を稼がないと赤字になるリスクも高いのですが、いったん損益分岐点を超えて売上高が増えれば、固定費比率がより高い方がより営業利益を大きくする効果が出てくるのです。
■ 次回に本格的説明をする決算短信の業績予想についてほんのさわりをご紹介
前章で説明した固定費のレバレッジ効果が、実務で立派な理論として採用されています。それは、決算短信における業績予想の実務です。東京証券取引所有価証券上場規程施行規則407条に、「直近で公表した予想値と、新たに計算した予想値との間に、次の変動幅がある場合には、『業績予想の修正』を公表しなければならない」というものがあります。
<業績予想の修正内容>
① 売上高 ±10%
② 営業利益 ±30%
③ 経常利益 ±30%
④ 親会社に帰属する当期純利益 ±30%
これは、長い実務を重ねてきた期間において観察された経験則として、すべからくどの業界でも、売上高が上下に10%動いたら、固定費のレバレッジ効果でその下の段階利益は上下に30%、すなわち3倍の変動幅で動くことが経験値から分かったので、このような比率が定められています。しかし、東京証券取引所も、開示財務諸表として、製造原価報告書(製造原価明細書)の提出を求めていないのに、現在のこうした固定費のレバレッジ効果が本当に、10%⇔30% の3倍となっていることをどうやって証明できるのでしょうか。しかも、固定費比率がどの業界でも一定であるとする仮定には無理があるとは思わないのでしょうか。
さてさて、10%⇔30% の関係を数式モデルで解き明かして、きちんとその原理を理解しておきたいですよね。その辺は次回までの宿題とさせてください。(^^;)
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(1)イントロダクション - CVP短期利益計画モデル活用の前提条件について」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(2)基本モデルを理解する - 数式モデルの成り立ちについて」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(3)基本モデルを理解する - チャートモデルで可視化 」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(4)チャートモデルを味わい尽くす - ビジネスモデル分析や利益モデリングを試みる!」



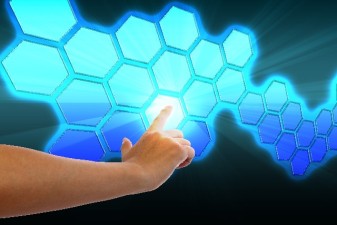
コメント