■ 財務諸表作成目的に基づき、売上高に対応する原価情報を提供する

原価計算基準にて様々な原価概念を3つの対立軸でまとめたのが、今回からご紹介する「基準四 原価の諸概念」です。基準四では、
① 製品原価に使う消費量と価格の算定基準
実際原価 と 標準原価
② 財務諸表上の収益との対応関係
製品原価 と 期間原価
③ 集計される原価の範囲の違い
全部原価 と 部分原価
の3軸、6種類の原価概念を順に説明しています。今回は、財務諸表(損益計算書)において、収益に対応する原価をどうやって見つけ出すか、という論点から、「製品原価」と「期間原価」について考察をしたいと思います。
では詳細な説明に入る前に、「基準一」から「基準六」までの全体像はこちら。

原価計算制度は、財務会計の世界で決算手続きを通じて、期間損益を確定させるために、原価情報を提供するために存在しています。期間損益を定義するために、収益(売上高)に対応する原価または費用の額を知る必要があります。その原価または費用の決め方に2つの方法があるというのが今回のテーマとなります。
これは、原価計算の目的のひとつ、「財務諸表作成目的」に基づくものになります。
■ 「費用収益対応の原則」が計上すべき原価と費用の算出方法を導く
まずは、原価計算基準の本文を確認します。
四 原価の諸概念
原価計算制度においては、原価の本質的規定にしたがい、さらに各種の目的に規定されて、具体的には次のような諸種の原価概念が生ずる。
(二) 製品原価と期間原価
原価は、財務諸表上収益との対応関係に基づいて、製品原価と期間原価とに区別される。
製品原価とは、一定単位の製品に集計された原価をいい、期間原価とは、一定期間における発生額を、当期の収益に直接対応させて、は握した原価をいう。
製品原価と期間原価との範囲の区別は相対的であるが、通常、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし、販売費および一般管理費は、これを期間原価とする。
財務諸表(損益計算書)にて、収益(売上高)と対応させる原価・費用の差額で期間損益を計算します。この収益を稼ぐのに適切な原価・費用を持ってくるという考え方を「費用収益対応の原則」といいます。

原価・費用は大別して3つに分類されます。「直接原価」「間接原価」そして「販売費および一般管理費」です。前2者は生産(調達)・販売される製商品に集計して、それが売れれば売上原価となりますし、それが売れ残れば、原価・費用とせずに期末棚卸資産として、貸借対照表に企業の所有財産として記帳されます。残りの販管費は、どれが売れ残りかを判別することが難しいので、発生したと認められる会計期間において、全額を原価・費用として認識することになります。
「直接原価」と「間接原価」の詳しい話は、下記過去投稿をご参照ください。
⇒「原価計算 超入門(8)原価計算における配賦とは - 費用収益対応の原則により間接費を棚卸計算させる技にすぎない」
ここではシンプルに説明を済ませます。
「直接原価」
例えば材料費。売れたものと売れ残ったもののそれぞれに、どれくらい材料費を投入したか個別に識別できると考えます。直接的に、材料費の受け払い(いくら入ってきて、いくら出ていったか)の記録を取って、会社の外に出ていったものをその期間の原価と認定します。
「間接原価」
例えば、労務費や製造間接費(製造機械の減価償却費や水道光熱費など)は、確かにひとつひとつの製品を作るために支出された原価なのですが、製品一つにいくら使ったかを直接的に把握することは難しい。そこで、一定期間に支出された金額を、同じ期間で製造された製品の個数で割り算して、製品一つ当たりの負担すべき間接原価を割りだすのです。これを会計用語では「配賦」する、といいます。
ここまで読むと、無理矢理「配賦」して製品一つ当たりの間接原価をひねり出すことと、支出額の全額を「期間原価」としてしまう「販管費」の厳密な区別が、計算構造の違いだけではできないことに懸命な読者の方は気づくはずです。これはこれで原価計算の主要な検討テーマになっています(別稿でこの論点について議論する予定です)。
ここでは簡単に、製造活動に関するものは間接費でも、無理矢理「配賦」して「製品原価」扱いにします。販売活動や管理活動に関する費用は、あまりに生産活動のアウトプットとしての製品の一つ当たりのいくらいくらと計算するには根拠がなさすぎなので、全部ひっくるめて、その会計期間の費用にしてしまえ、という少々乱暴なお話なのでした。
■ 区別が微妙な「製品原価」と「期間原価」の間にあるものとは?
別のチャートで、もう一度「製品原価」「期間原価」を区別したものを図解してみます。

あらあら、このチャートでは、「直接原価」「間接原価」から構成される「製品原価」と、直接P/Lに集計される「期間原価」の他に、「非原価」という名称ながら、そのままP/Lに含められる項目が一番下に鎮座しております。
ここには、原価計算手続きにつきものの「原価差異」の取り扱いが次の論点として控えています。「原価差異」は、予定原価や標準原価と実際原価の差分を意味しています。原価計算基準では、原則として「実際原価」を真実の原価と認定します。
ここで「原則」というのは、正常性のあるものだけが原価扱いで、異常性がある場合は、非原価項目として、営業外費用や特別損失としてP/Lに計上されることを意味しています。つまり、製品一つ当たりの●●原価という「製品別計算」のプロセスから外して、その全額をドンブリ勘定で期間原価としてしまうのです。
話を「原価差異」に戻しますと、「実際原価」の性質を重要視する論者は、「原価差異」の異常性を軽視し、それも含めて「製品原価」を構成する「実際原価」を厳密に計算しようと試みます。その場合には、原価差異であっても、売上原価と期末棚卸資産とに切り分ける計算手続きを必要とします。「製品原価」は横文字を使うと「プロダクト・コスト」です。「実際原価」を重視する派は、原価差異は「プロダクト・コスト」扱いします。
一方、「標準原価」や「正常性」を重視する一派は、「原価差異」は、その全額を「期間原価」、横文字でいうところの「ピリオド・コスト(ピリオディック・コスト)」扱いにします。原価差異の異常性に着目すると、その部分は「非原価」ということになります。それでも、上記の通り、「非原価」項目であって、原価性なし、という認定を受けたとしても、営業外費用や特別損失として全額P/Lに計上されるので、どちらにせよ「期間原価」に違いないのですが。
■ もっと細かい特論:製品原価に算入される販売費および一般管理費も存在する
学問とは、概念を分類するのがお仕事です。分類すると必ず例外が発生します。
光合成するものが植物、自らの意志で移動ができるものを動物と定義したら、ミドリムシ(ユーグレナ)は、光合成しますが、鞭毛を使い自らの意志で動くことができます。キノコは光合成をしません。じゃあ、菌類は植物とは別の区分で、、、キリがありません。リンネの2界説でだめなら、ホイタッカーの5界説。そのうち、ウースの3ドメイン説ですか。。。(^^;)
閑話休題
(1)長期請負工事
企業会計原則より。
第二 損益計算書原則
三 営業利益
F 販売費・一般管理費の計上と営業利益の計算
営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して営業損益計算の区分に記載し、これを売上原価及び期末たな卸高に算入してはならない。ただし、長期の請負工事については、販売費及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入することができる。
(2)試験研究費
企業会計原則注解より。
注15 将来の期間に影響する特定の費用について
(貸借対照表原則一のD及び四の(一)のC)
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。
こちらは簡単なコメントを付します。「試験研究費(租税特別措置法)」は、①期間費用、②固定資産、③製造原価の3つの処理方法が詳しい内容別に定義されています。
「研究開発費(研究開発費等に係る会計基準)」は、原則が「期間費用」で例外が「製造原価(製品原価)」です。IFRSは原則と例外がひっくり返っていますが。
まあ、本稿は原価計算(入門編)。その辺の原価計算のラビリンスは次の中級編まで取っておくことにしましょうか。
逃げてませんよ。(^^;)
⇒「原価計算基準(1)原価計算の一般基準の体系を整理 - ざっと原価計算基準の世界観を概括してみる!」
⇒「原価計算基準(2)原価計算の目的 - ①財務諸表作成目的、②価格計算目的の盲点を突く!」
⇒「原価計算の歴史 - 経営課題の変遷と原価計算技法・目的の対応について」
⇒「原価計算基準」(全文参照できます)



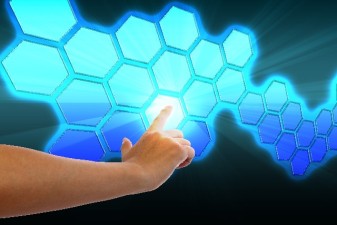
コメント