原価計算の目的を再確認
原価計算は制度会計では要請されていない製品単位の原価を求めることから、管理会計の独壇場であると思われているかもしれません。実は制度会計(財務会計)においても、決算手続き上で期末棚卸資産と売上原価を峻別することにより、期間損益の認識と測定(これらを合わせて計上という)に役立つことを原価計算の目的としています。
原価計算の目的は「原価計算基準」の「いの一番」である第1条に次のように列挙されています。
① 財務諸表作成目的
② 価格計算目的
③ 原価管理目的
④ 予算管理目的
⑤ 基本計画設定目的
この記事をお読みいただければ、まずは「②価格計算目的」とともに原価計算が誕生し、会計監査の厳格化(財務会計の制度化)により、「①財務諸表作成目的」が確立していったことが分かります。
では今回取り上げる条文を確認してみます。
第二節 原価の費目別計算
原価計算基準(原文)
九 原価の費目別計算
原価の費目別計算とは、一定期間における原価要素を費目別に分類測定する手続をいい、財務会計における費用計算であると同時に、原価計算における第一次の計算段階である。
「財務会計における費用計算」というのが、「①財務諸表作成目的」に対応する計算機構を提供することにつながっています。それで、今回の説明を唐突に原価計算の目的から始めたわけです。
そのほか、「一定期間」ってどれくらいの時間の長さを想定しているのか? 「原価要素」と「費目」は違うものなの? 「第一次」の計算段階ということは、「第二次」とか「第三次」があるの? という素朴な疑問が生じたはずです。いや、生じましたよね?^^)
ほかの教科書ではとくとくと説明してくれない基本中の基本をさらって文字化(可視化)するのが今回の試みです。
原価計算の計算ステップは3段階が基本
原価計算というものは、基本形として、次の3ステップに従って製品原価を求めるものとされています。応用系として、ABC(活動基準原価計算:Activity Based Costing)、スループット会計などがありますが、いずれも、第2ステップの部門別計算と第3ステップの製品別計算の仕方がそれぞれの哲学に従ってデザインされているだけで、大きくは、この3ステップの枠組みの中にきちんと収まっています。
上の記事でも触れているのですが、3ステップは、
① 費目別計算
② 部門別計算
③ 製品別計算
のことです。

費目別計算では、材料費・労務費・製造間接費・販管費など、製品の製造・販売に要したコスト(原価と費用をひとくくりで表現するカタカナ用語です)を明確にはじくことを行います。
部門別計算では、直接製品に結びつけることが難しいコストは、製品との関連で分類した場合の「間接費」として、いったん、「原価計算基準」が制定された当時の認識としては、補助部門に集計します。補助部門から主要部門に補助部門費を配賦することで、主要部門から各製品にチャージ(振り分け)する前裁きとなる準備動作です。
そして、直接費はそれぞれの費目を直接的に製品に賦課し、主要部門に集めておいた主要部門費と補助部門費を合わせて間接費として、製品に配賦します。これで、製品単位当たりの製品原価が分かる、という仕組みになっています。
ABCとかスループット会計といっても、そんなにビビる必要はありません。所詮、部門別に間接費を集計して、それを主要部門に配賦してから、改めて主要部門から製品に配賦するのではなく、「活動」とか「スループット」を意識するだけのことで、「部門」を使用する代わりに、「活動」や「スループット」という概念を用いているだけです。まあ、計算結果としての製品原価は違いますけれど。^^;)
原価計算基準の全体構成を復習する
原価計算ステップが分かったところで、「原価計算基準」が想定している原価計算ワールドの中で、この3ステップがどういう位置づけにあるかを、全体目次をチャートにまとめたものを見ながら理解していきましょう。

「原価計算基準」を縦に箇条書き+インデントで表現すると次のようになります。
- 第1章 一般的基準
- 原価計算制度
- 特殊原価調査
- 第2章 実際原価計算
- 第1節 製造原価の分類基準
- 第2節 費目別計算
- 第3節 部門別計算
- 第4節 製品別計算
- 総合原価計算
- 単純総合原価計算
- 等級別総合原価計算
- 組別総合原価計算
- 個別原価計算
- 総合原価計算
- 第5節 販管費の計算
- 第3章 標準原価計算
- 第4章 原価差異の算定・分析
- 第5章 原価差異の会計処理
一番広い部分から、原価計算は、制度会計で決算報告する(財務諸表を作成する)ための「原価計算制度」のものと、個別の意思決定のためにデータ提供・分析を行う「特殊原価調査」の2つに大別されます。
「原価計算制度」の方は、単価と消費量のよりどころを「実際」とするか「標準(原価標準)」とするかで、「実際原価計算」と「標準原価計算」に大別されます。この2つは計算後に突き合わせて、原価差異を計算・分析する必要があるので、その内容は写し鏡として同様になっている必要があります。それゆえ、「原価計算基準」では、双方に重複する内容はすべて先に登場する実際原価計算の規定の中に書き込んであります。
実際原価計算(標準原価計算でも同様)では、費目別計算→部門別計算→製品別計算の手続きに従って製品1個当たりの製造原価を求めることになります。製品別計算の段階になって、直接費や間接費をどうやって、製品別に集計するか(製品別に割り当てるか)の方法論の種類に、「総合原価計算」や「個別原価計算」という便法がある、という建付けになっているのです。
みなさんは、「費目別原価計算」「部門別原価計算」「製品別原価計算」という日本語を教科書等に目にしたことがあるかもしれません。こうした言葉遣いは、原価計算の世界では、実は厳禁(NG)なのです。
「原価計算」という用語は、「原価計算基準」において、直接費と間接費をどうやって製品単位に集計するかの方法論を識別する「総合原価計算」「個別原価計算」という種類を表すか、原価の根拠を歴史的原価、正常原価、予定原価のいずれを採用するかで識別する「実際原価計算」と「標準原価計算」の区別でしか用いません。
ただし、基準四 原価の諸概念(三)全部原価と部分原価の規定に基づき慣行上、「全部原価計算」「直接原価計算」という用法は認められています。しかし、「全部」「直接(部分)」はそれ単独で使用されることは少なく、「全部実際原価計算」とか、「直接標準原価計算」というネクサス(nexus)で用いられることが一般的です。
ちなみに、これらの語順には一定の慣行が存在し、「全部or直接」+「実際or標準」+「総合or個別」の順で結合して表現することが最も一般的です。
例えば、
「全部実際総合原価計算」
というふうに。
簡単にまとめると、製品原価を求める行為を指して「●●原価計算」する、と覚えておけば十分です。
原価計算期間として適切な「一定期間」はどれくらいの長さか
これも原価計算の初学者を迷わせる珍説や説明不足が多々あるところです。皆さんはおそらく「原価計算期間は一般的には1か月である」という一文だけを目にしていることと思いますがいかがでしょうか。
これを詳細に語りだすと、それだけで記事1回分の文字量になるので、ここではできる限りかいつまんで説明します。不等式を用いると次にように表現することができます。
- 正常原価が観察し得る期間 = 原価計算期間 ≦ 決算期間
原価計算は、制度会計における決算手続きの中で、期末棚卸資産の評価額と売上原価を峻別する必要があるため、決算を超えては制度会計の要請に応じることができないので、これより短い期間となります。
一方で、あまりに短い期間だと、十分に季節変動を織り込んだ正常原価の水準の見積りが立たない恐れがあり、原価管理、予算管理、適切な値決め、その他の原価計算目的を達成することが困難であるだけでなく、事務手数ばかりがかかり、対価として得るものが何もなくなってしまいます。
そこで、財務上の会計慣行として、月次決算として各勘定を締めて金額の妥当性や会計処理の適切性をチェックするタイミングに合わせて、内部的な原価計算期間とする例が多いため、逆にそれをもって教科書が「1か月」と言い切っている、というのが実態です。
ちなみに、原価計算の教科書としての不朽の名作(古典)である岡本清著「原価計算(六訂版)」P21には、製靴業の見積原価計算期間は「3か月」、製糸業では、原料とする繭の値段が春繭の場合には、7月後半から8月に決まるので、春夏秋の「蚕期」ごとに原料費の計算をすることが多い、という記述がきちんと説明されています。まあ、今時、靴の原料の皮革、絹製品の原料の繭の単価決定を例にだされても、ピンと来ないかもしれませんが、そこは想像力で補ってください。^^)
また、1か月というのも実は曲者です。一般常識的には、月初日から月末日で1か月の原価計算期間としている企業が製造業では圧倒的に多いと思います。ご存じの通り、月には、大の月、小の月があるため、カレンダー通りに月別の原価計算をやると、緻密に考えれば考えるほど、この日数のブレは原価管理にとって大敵として原価管理担当者の目の前に立ちはだかります。
この場合、流通業が販売・マーケティング領域でそうしているように、1年を週で割って52週とし、それを13期間(4週間で1期)で管理する、そもそも52週で週次管理するという方法があります。また外資系で多く採られている方法として、月末日起点ではなく、週数を調整して12か月に按分するというものもあります。
原価要素と費目は別物か
これも、多くの教科書では混同されて(特段意識もされずに)使用されていますが、歴史的経緯からすると、大いに違いがあります。^^)
昭和17年に、当時の企画院(戦前期の内閣直属の物資動員・重要政策の企画立案機関)が定めた「製造工業原価計算要綱」において、材料費、労務費、経費という具合に、生産手段の入手経路と利用手段の別にこれが原価要素である、という一律的な定義がなされていました。
昭和37年に企業会計審議会によって定められた「原価計算基準」では、基準八「製造原価要素の分類基準」にある通り、多様な原価に対する視点からすると、一義的にこれは絶対に経費だ、と言い切ることは逆に原価計算の多様な目的の阻害要因になると考え、形態別分類に始まって、機能別分類、直接費・間接費、変動費・固定費、管理可能費・管理不能費というそれぞれの使用目的に応じた分類を行うことにしました。その分類に従った区分表記を「費目」と呼ぶわけです。
まあ、令和の時代、昭和17年といわれてもね~。^^;)
(そういえば、この記事を書く数日前、中曽根元首相の訃報がありました。合掌)
みなさんからご意見があれば是非伺いたいです。右サイドバーのお問い合わせ欄からメール頂けると幸いです。メールが面倒な方は、記事下のコメント欄(匿名可)からご意見頂けると嬉しいです。^^)
(注)職業倫理の問題から、公開情報に基づいた記述に徹します。また、それに対する意見表明はあくまで個人的なものであり、過去及び現在を問わず、筆者が属するいかなる組織・団体の見解とも無関係です。





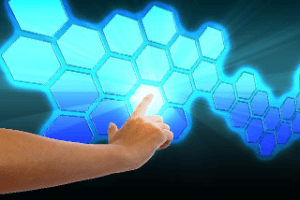
コメント