■ 「配賦」計算のそもそもに迫る!

原価計算を学習したり実務で扱ったりする際に、避けて通れないのが「配賦計算」です。本稿では、配賦計算におけ実務的なテクニックをずらずらと紹介することはせず、そもそも配賦計算を必要とする会計の考え方について基本的な所から説明したいと思います。基本的な思考を学習しておけば、千変万化する原価計算実務の世界において、採るべき配賦計算ロジックについて最適な判断が下せるというものです。
それでは、原価計算において「配賦」を必要とする会計原則が2つ存在します。
① 全部原価計算主義
② 費用収益対応の原則
①については、本シリーズの前回で触れました。製品やサービスを構成する原価については、直接費だけでなく、間接費も漏れなく製造原価(売上原価)とする必要性があることから、間接費を製品・サービスのひとつひとつに割り当てなければなりません。
(参考)
⇒「原価計算 超入門(7)全部原価と直接原価の違い」
ここでは、より本源的な「② 費用収益対応の原則」による要請ポイントから説明を開始したいと思います。
なお、「共通費」と「固定費」の違い、テクニック的な「配賦基準(配賦する際に使用する按分方式)」についての基本的な解説は、次の過去投稿で解説済みです。
⇒「固定費の配賦の目的をきちんと認識していますか? -共通費と固定費の違い」
■ 「費用収益対応の原則」の考え方によって損益計算書(P/L)は計算されています
「費用収益対応の原則」というのは、「会計原則」における「損益計算書原則」で、いの一番に説明されている概念です。損益計算書(P/L)とは、とある会計期間における利益を計算するための財務諸表であり、いわゆる「期間損益」を計算するために、「収益(平たく言うと売上高)」から、それを顧客から得るために犠牲にした「コスト(原価と費用、損失を含む呼び名)」を差引計算で行っています。
この時、期間損益を過大に見せたい場合は、差し引くコストを少なくすればよいですし、一方で期間損益を過小に見せたい場合は、差し引くコストを多くする誘惑に、経営者をはじめとする企業会計関係者はかられます。正しく企業業績を測定する、すなわち期間損益を適正に計算するためには、企業外部から得た「収益」と、その収益を得るために企業内部で犠牲にされた貨幣的価値(ここではコストと呼んでいる)だけを選別して、収益から差し引くことで満足する結果を得ることができます。
ちなみに、一般的には、収益からコストを差し引くという引き算を頭の中でイメージされるのが通常ですからそのように説明していますが、会計、とりわけ複式簿記の世界では、最初から、引き算という計算構造を持ち合わせていません。あくまで、「収益」に対して、しかるべき「コスト」を提示し、その差額を「利益」という勘定に振り替えるという計算構造であり、そこには足し算しかありません。そうです。会計(複式簿記)とは、つまるところ、小学1年生の算数レベルで理解できる(はず)の計算構造に過ぎないのです。
それゆえ、差引計算ではなく、正しいペアリングになる「収益」と「コスト」を対比させるイメージで、「対応の原則」という名が付けられています。
「収益」とは、一般的には売上高・営業収益を意味します。その稼得のために、一般的には経費を使ったり、商品や材料を仕入れたり、会社で働く従業員への賃金を支払います。その経費や仕入れ、賃金がここで言うコストとなります。しかし、経営者が自分の都合で期間損益を操作できないように、コストを3つに大別(アカデミックには4分類ですが、ここは入門レベルなので3つにしておきます)して、経営者の恣意性に捉われないコストの対応を測るように入口から対応方法を分けています。
■ 「配賦」は「費用収益対応の原則」に則って「間接原価」を製品にひもづける作業
「費用収益対応の原則」には、対応基準が2つあります。

① 個別的対応
個々の製商品・サービスを媒体として対応関係を確認できる対応方法
② 期間的対応
個々の製商品・サービスとの関係性が曖昧なため、それらが販売された事実と期間的な対応関係を確認する対応方法
例えば、八百屋さんがニンジンを1つ仕入れれば、その購入代価は、個別的対応できます。生鮮食料品が期末に廃棄されずに棚卸計算されるとすれば、売れなかったニンジンは在庫として、貸借対照表(B/S)に「棚卸資産」という勘定で取り分けられて、期間損益計算から排除されます。そして、次の会計期に売れれば、その在庫評価金額が、その会計期でのコストとして、再び「費用収益対応の原則」に則り、P/Lに計上されます。
しかし、八百屋を営んでいく上で、照明や自動ドアを動かすために使用される電力料はどうやって、売られていく野菜にコスト対応すればよいでしょうか。ニンジン1本あたりの電力料を棚卸計算することは、あまりに計算合理性に欠けるため、会計原則では、製商品・サービスのひとつひとつに跡付けることが難しいコストは、それが適正に発生した会計期間にそのまま団子として費用計上することを許したのです。一般には、「販売及び一般管理費」として、売上総利益と営業利益の間に計上される性質のものです。
製造業において、自社製品を作り出す工場における使用電力料は、一般的には「販管費」とすることが許されていません。それは、同じ電力使用に伴い発生したコストであっても、工場で使用された = 自社製品の製造のために犠牲にされたコスト、と認定され、「間接原価(間接費)」として、製品ひとつひとつに、精密にいくらかかったか不明にもかかわらず、製品原価の構成要素として、棚卸計算対象とする、つまり、製品1単位当たりの「単価」に含めることを会計法規で強制したのです。そのための会計技法が「配賦」なのです。
確かに、販売部門や本社統括部門が使用した電力は「販管費」で、製造部門が使用した電力は「間接原価」という区別は、限りなくグレーゾーンに近いものであると言わざるを得ません。まだ企業が小規模の場合は、ひとつの建屋に製造部門と管理・販売部門が同居していることはよくあることであり、そうした中で、その建屋で発生した電力料を「販管費」と「間接原価」に区別することは至難の業です。実務的には、それぞれの部門やフロアで子メーターを用いて測定でもしていない限り、部門別の使用面積比や人数比で、建屋全体で消費した電力料を按分(これも配賦)することになるでしょう。それゆえ、「配賦」計算には最初から、曖昧さが残り、合理性や納得性に欠けるケースが後を絶たないのです。
■ 「配賦」計算構造は、原価計算フローにおいて2カ所に登場する
原価計算は、次の3ステップで行われることは既に説明済みです。
① 費目別計算
② 部門別計算
③ 製品別計算
(参考)
⇒「原価計算 超入門(1)原価計算の見取り図」
「配賦」計算は、②の部門別と③の製品別の2カ所で行われます。

とある製造業の工場における配賦計算を例にとります。この工場では、使用電力は補助部門である工場管理部で一括して管理されており、製造1課で製品Aを2つ、製造2課で製品Bを1つ製作しています。製造1課は、製品Aを2つ製作していますが、1つあたり1時間の所要時間がかかるので、合計して2時間の製作時間を要します。一方。製造2課は、製品Bを1つ製作しており、こちらは4時間かかるので、製造1課と製造2課の総作業時間に占める比率は、1:2となります。この比率で、工場全体の使用電力料を按分します。
上例で製造1課に配賦された電力料:30円は、最終的に各製品原価を構成するために、製品単位にまで配賦される必要があります。ここでは話を簡単にするために、同種の製品Aを2つだけ製造していることから、単純に個数割りとしておきましょう。ここでも、実務では、直接材料費や直接作業時間などを「配賦基準」として使って配賦することも考えられます。「配賦基準」選択の是非は、前述の過去投稿を参考にしてください。
■ (補論1)直接労務費は本当に賦課(直課)されているのか?
よく、直接労務費は「直接費」なので、「賦課(直課)」されるべきものである、という言説がまかり通っています。一般的な学説としても、簿記の試験でも、そのように理解・認識されていますが、実務感覚から、筆者は、直接労務費であろうとも、実のところは「配賦」されていると考えています。
「直接労務費」が「直接費」であるためには、製品1つ1つに、正確に直接作業に従事した要員にかかる人件費が乗せられるべきです。そのためには、製品1個を製作するのに、
何の擬制的ロジックも使用せずに、純粋のその製作物にかけた人件費のみを取り出す必要があります。しかし、現実には、
① 一人の直接作業員(直接工)が、複数の製品の製作に従事することが通常である
② そのひとつひとつの製品にかけた作業時間を実績ベースで計測することは実務上困難なことが多い
③ 一人の直接作業員にかかる人件費(労務費)をその直接作業員の総作業時間で割り算して労務費単価を計算し、ひとつひとつの製作物作成の所要時間にかけて労務費を計算することが多い
このことから、事実上、一人の直接作業員という間接部門にも擬せられる原価集約単位から、作業時間比例でひとつひとつの製品に労務費を「配賦」していると考えられなくもないのです。
厳密に言えば、複数の直接作業員が総出でたった一つの製作物に全精力を注ぎ、その製作物単位が原価計算対象である場合のみ、全員の労務費はその製作物単位に賦課(直課)されているといえます。これは、個別原価計算(プロジェクト別原価計算)でも特殊なケースにのみ当てはまる特殊例です。
総合原価計算を採用している場合は、いかに直接作業員(直接工)という名で呼ばれている要員の労務費を賦課(直課)していると言っても、それは、直接工の保有工数を母数とした時間比例で配賦しているにすぎません。さらに、個人としての直接工の労務費を集計するのではなく、実務では、製造ライン別や職能等級別に直接工にかかる労務費を集計して、時間比例で製品に賦課(筆者はそれをあえて配賦と呼ぶ)しています。直接工をグルーピングして一つの部門に見立てて、作業時間で単に配賦しているにすぎない。こう言い切ってしまうと、市販の教科書を全否定してしまいますのでここだけの話にしておいていください。(^^;)
■ (補論2)「配賦」計算はどこまで正しいのか?
なお、本稿で最後に言いたいことは、採用する「配賦基準」の種別によって、最終的に計算される製品別原価が異なってしまうことです。ここからはあくまで私見ですが、サイエンスとして唯一解の存在を信じる人は、学問としても、実務としても「会計」をあまりお勧めできません。現場・現実・現物を注意深く観察し、何が経営的意思決定に役立つ計数情報となるか、ステークホルダーが納得する会計数値となるか、合意形成を皆の協力に基づいて求めるのが会計だと考えています。残念ながら、最初から答えが用意されていないのが会計で、その顕著な例がこの「配賦」だともいえます。
前述の例で、電力料金を直接工の作業時間を配賦基準にして、製造1課と製造2課に配賦し、その結果を個数割でさらに製品Aの各生産物に配賦しました。そこで、部門別配賦の方を、作業時間ではなく、直接材料費金額比例にしてみて、両者の原価を比較してみましょう。

本当に、会計学は簡単な四則演算だけで簡明に結果が得られることが多くて、完全文系人間の筆者はとても助かっています。(^^;)
作業時間比例と材料費按分とでは、最終的に製品Aと製品Bの製造原価や単価が異なってしまいます。さらに、製品Aは2個製作されているので、その1つが期末の在庫に回った場合は、2期間の期間損益および在庫評価額も変動してしまい、決算数字にも影響してしまいます。
それゆえ、配賦基準の選択は、製造現場の原価能率の測定や、儲かり度具合を測る経営的意思決定、さらに投資家や債権者、課税当局への業績報告にも多大な影響を与えてしまうことを忘れてはいけません。
さまざまな、配賦基準の選択方式が存在しますが、入門編ですので、本稿では詳しくは触れませんが、特に制度会計が絡む原価計算の場合に配賦基準を選び出すとき、筆者の留意点を下記にまとめます。
(1)相関性
原価要素の発生が、原価計算対象の製造・提供プロセスにおいて、価値創設に対して相関関係(比例関係)を説明することができるか
(2)共通性
原価要素を配賦すべき配賦対象に共通の配賦基準であるかどうか
(一部でも、その配賦範囲から外れてしまう計算メカニズムは、真に正しい按分を行っていない可能性が高い)
(3)経済性
その配賦基準は、データとして入手・計算が容易で、運用コストが高つかないものであるか
この3つから、上例で、電力料を「直接材料費」ではなく、「直接作業時間」で配賦した方が、相対的に(1)相関性がより担保されているとは思いませんか?どちらも(2)共通性は保持していますが、(3)経済性については、「直接材料費」の方がやや上回っているかもしれません。しかし、(1)~(3)は重要性ランクで並べてあります。その点もお含みおきくださいませ。
結局のところ、配賦計算は、既に発生(時には支出)済みのコストをどう切り分けて、原価計算対象に配り尽くすかということ。巧妙な配賦ロジックを追求したところで、そもそものコスト総発生額を減らすことには、直接は貢献しません。いつも、配賦計算は、発生済みコストをどう仕舞い付けるかの後始末が役割。
「いくら正しい(と思われる)配賦基準を選択しても、それだけで企業が儲かるわけではない」






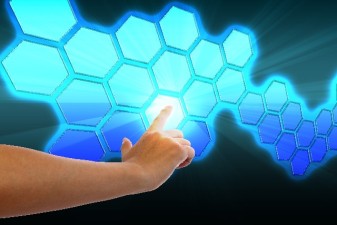
コメント