50の手習い、また増やす
最近、クライアント訪問をさせて頂いている中で、「管理会計一徹30年です」というキャッチフレーズを多用している自分に気が付きました。そして、「管理会計」のプロフェッションを公的に認証してくれる制度は一体何か、という基本的な疑問に立ち返ることができました。
「管理会計」のプロフェッショナルは、世の中的にはどういう人のことを言うのでしょうか? 具体的には、管理会計実務の経験が長く、理論も勉強している人が要件に当てはまるのかもしれません。
しかし、それはあくまでその人の内面的な評価基準で測られているので、客観性をいまいち確認することが難しいものです。ある程度、お勉強して、外形標準的に、管理会計について何かを知っている、何かができる、ということを明示的にする必要があるのではと思うようになりました。
そこで、とりあえず、最終的に協会に会員登録して「米国公認管理会計士(USCMA)」を名乗るかどうかは脇に置いておき、勉強だけはしておこうと決意しました。
50の手習いをまた一つ、増やすことになります。
USCMAに的を絞った理由
会計に密接に関係する資格には、USCMA以外にも、以下のようなものがいろいろとあります。
- 公認会計士(JICPA)
- 税理士
- 米国公認会計士(USCPA)
- 米国税理士(EA)
- 公認内部監査人(CIA)
- グローバル勅許管理会計士 (CGMA)
- 日商簿記検定
- 証券アナリスト (CMA(R))
- CFA(R) (CFA協会認定証券アナリスト)
- BATIC (国際会計検定)(R)
- FASS検定 (経理・財務スキル検定)
- 国際会計基準 (IFRS) 検定
- フィナンシャル・プランニング技能検定
- 中小企業診断士
- 経営士 など
ここではまだ書ききれないほど、会計に関する資格や技能検定があります。
その中から、とりあえず勉強しておこうと考えたのが、米国管理会計士(USCMA)でした。
実は、同じ英語で受験という条件ならば、グローバル勅許管理会計士 (CGMA)という選択肢もありました。

迷いに迷ったのですが、いずれにせよ、管理会計は資格・免許による独占的な業になり得ないため、また、今回の勉強の動機も、30年の実務経験の整理が目的なので、普段ならあり得ない、簡便法でUSCMAに決めました。
それは、資格試験支援サービス業のTACにコースがあるかないかでした。
USCMAとは何ぞや?
まず、略称からなのですが、単にCMAと言ってしまうと、日本では、日本証券アナリスト協会が展開している証券アナリスト(CMA: Certified Member Analyst) と被ってしまうので、資格受験業界では、「USCPA」と頭に「米国」を意味する「US」を付けることが慣例になっているそうです。

改めて、USCMAの説明をさせて頂くと、IMA(Institute of management Accountants)管理会計士協会が主催する資格で、USCPAと違い、何かの独占業務を可能にするものではありません。
試験合格後、2年以上の実務経験(財務会計・管理会計・財務分析・予算編成・経営コンサルティング・監査など)を持つことが認められば、名刺で「米国公認管理会計士(USCMA)」と名乗れるだけのものです。
しかし、受験が英語によるものなので、英語+管理会計のベースがあるビジネスパーソンとして認められやすくなるメリットがあります。 サイトでは、全世界140ヵ国に90,000人以上の会員がいる、というアピールがありましたが、USCPAは米国だけで、665,000人以上、日本ではホルダーを含めると36,000人です。
IMAのホームページ(もちろん英語です)
IMAとUSCMAを解説している日本管理会計教育協会のページ(もちろん日本語です)
知名度と必要学習時間と必要経費の比較でいうと、USCPAのほうが、高くて難しいのはもちろんのことです。
しかし、なんといっても、試験内容がずばり「管理会計」なので、USCPAに比べて、あまり興味のない監査論(あくまで筆者個人の好みで、現職とは全く無関係の意見です)で慣れない英語学習をおこなう辛さを想像すると、カリキュラムを眺めているだけでも、心がうきうきしてきます。
Part1/Financial Planning, Performance and analytics (財務計画、業績管理と分析)
| 出題範囲(英語) | (日本語) | 割合 |
|---|---|---|
| External Financial Reporting Decisions | 財務諸表報告の決定 | 15% |
| Planning, Budgeting and Forecasting | 予算の計画、編成 | 20% |
| Performance Management | 業績管理 | 20% |
| Cost Management | 原価管理 | 15% |
| Internal Controls | 内部統制 | 15% |
| Technology and analytics | テクノロジーと分析 | 15% |
Part2/Strategic Financial Management (戦略的財務管理)
| 出題範囲(英語) | (日本語) | 割合 |
|---|---|---|
| Financial Statement Analysis | 財務諸表の分析 | 20% |
| Corporate Finance | 企業財務 | 20% |
| Decision Analysis | 意思決定分析 | 25% |
| Risk Management | リスクマネジネント | 10% |
| Investment Decisions | 投資意思決定 | 10% |
| Professional Ethics | 倫理 | 15% |
どの出題範囲をみても、常日頃、それで飯を食べているネタそのものです。純粋に学習時間が取れないとか、そもそも英語がNGだったとか、試験なので、いわゆるアウトプット学習(問題慣れ)が肌に合わなかった、という受験そのものに内因するハードルがそれほど高くない場合、これまでの経験値は一体何だったのか、やっぱり偽物だったのか? という疑問符がついてしまいます。
誰ですか? 「最後の『倫理』だけは、お前には無理(NG)だ」とおっしゃるのは? それは自覚しています。もし不合格ならば、「倫理」がNGだった、ということにしておいてください。その方が、傷が浅くて済みます。
もし歓迎すべき結果に至らなければ、これまで提供させて頂いた、経営管理・管理会計サービスの真贋が問われかねないリスクがありますね。でも、これをブログで公開する意味があるんです。
資格勉強の実況中継をブログでやる恐ろしさ
ええ、多くの仕事関係者も当ブログを読んでいただいているので、「今更資格勉強かよ」「もし受からなかったら、どう落とし前付けるの?」という声をお寄せいただくことも予想できます。
念押しですが、本当に、今更なので、最終ゴールは合格ではないんです。資格の受験勉強を通して、これまでの30年の経験値を再整理したいだけなんです。ええ、事前の言い訳では決してありませんよ。^^;)
えらそーに、クライアントに管理会計の知識をひけらかして、それでおまんまを食べさせていただいている身分なので、いくら英語での受験とはいえ、全く歯が立たなかったとしたら、それはそれで大問題です。
こういうことは、オープンにしていたほうが、後々よろしいと思い、始める前にディスクローズした次第です。
プロフェッショナルであることの定義は、「資格制度による Certified 」もありですが、それで「飯が食えているか」という条件も大事です。お陰様で、後者の条件は何とか満たしてきましたので、今年は前者の「Certified」を受けることを目指してみようかと思い立ちました。
これは、100%言い訳なのですが、TACの通信講座の有効期限は2021/3/31までで、その中にビルドインされているBeckerのWebコースは、2022/1/31までです。年3回も受験の機会が与えられ、2科目は受験科目毎の合格が認められています。
最長、2022年1月受験の日まで、5回もチャンスがあります。気長に、頭の中の再整理をしながら、勉強を続けていきたいと思います。勉強を進めていく中で、ブログで公開したいぐらいの気づきがあれば、折に触れ、投稿していきたいと思います。
可能でしたら、受験仲間ができれば最高なんですがね。。。




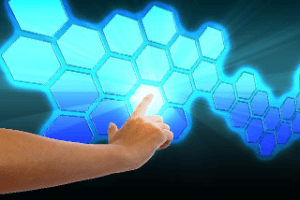
コメント