「管理会計」するために「管理不能費」の定義が必要な理由
管理会計にとって皮肉的なのが、「原価計算基準」にて「管理可能費」と「管理不能費」とが区別して定義されていることです。「管理」会計という名前の通り、コストを管理するための技法にも関わらず、自ら管理「不能費」を明らかにするという立場をとるのです。
これは逆説的に、管理不能費を一定の条件下で上手に排除し、管理可能費だけに純化してくれれば、その範囲内では絶妙に管理可能費をコントロールしてあげるよ、という宣言と受け止めることもできます。
まずは、条文の確認してみます。
第一節 製造原価要素の分類基準
八 製造原価要素の分類基準
原価要素は、製造原価要素と販売費および一般管理費の要素に分類する。製造原価要素を分類する基準は次のようである。
(五) 原価の管理可能性に基づく分類
原価の管理可能性に基づく分類とは、原価の発生が一定の管理者層によって管理しうるかどうかの分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを管理可能費と管理不能費とに分類する。下級管理者層にとって管理不能費であるものも、上級管理者層にとっては管理可能費となることがある。
原価計算基準(原文)
「原価計算基準」では、原価計算の目的を、
① 財務諸表作成目的
② 価格計算目的
③ 原価管理目的
④ 予算管理目的
⑤ 基本計画設定目的
の5つと定められています。このうち、「③原価管理目的」とこの管理可能性で原価要素を分類する所作が一番強く結びついています。③を介して、「④予算管理目的」に通じているのです。
そのロジックはこうです。あなたがコストの発生と経済資源の使用のタイミングとその物量(物量は究極的には金銭の消費につながり、会計的な金額でその消費物量の多寡が示されることになります)を自分でコントロールできる権限の範囲内においてしか、そのコストと物量の多寡に責任が持てない、という基本原則が貫かれているのです。
例えば、あなたが工場長の立場にあったとして、営業部に所属する部員の交際費の使い方に直属の上司でもないのに、口を出すことができるでしょうか? それは、責任会計制度においては、一義的には営業部長の管轄下です。営業部長は、自分の管轄下の営業部門の予算に責任を負っていますが、その責任を負えるのは、営業部で発生するコスト、およびそのコスト発生の原因となる営業活動のタイミングと内容について、差配する権限があるからです。
それゆえ、管理対象が、「管理可能費」であることは、「③原価管理目的」を達成するためには必要条件であり、原価管理が可能である状態は、「④予算管理目的」を達成するための必要条件になっているのです。
誰にとって管理可能費かを鋭く解析してみる
上例では、営業部門の交際費の支出は、工場長の会計責任の範囲外だから、「管理不能費」である、という説明をしました。所属する組織・部門の違いだけが、「管理可能費」と「管理不能費」を区別する唯一の手掛かりなのでしょうか?
原価計算論におけるコストの「管理可能性」は、まるで法律家が条文を適切に解釈するように、緻密で繊細なロジックと実務からの経験を積み上げた先に立ち現れるものです。
一般的には、「管理可能費」は次の三要件をすべて満たすことが求められているとされています。
① 責任能力:特定の管理者にとって管理可能であること
② 回避可能性:一定期間において管理可能であること
③ 影響力:特定の管理者の判断に基づいて重要な影響を及ぼすことができること
「①責任能力」は、条文にも「下級管理者層にとって管理不能費であるものも、上級管理者層にとっては管理可能費となることがある」とある通り、職務権限と結び付けて考えられるものです。
仮に、あなたが製造工程におけるライン長だったとして、部下の配員計画と、部下の給与査定の双方に権限があれば、自工程で発生する労務費の「単価差異」と「時間差異」に責任能力があるといえるかもしれません。
しかし、部下の給与査定と、どのラインに誰を配置するかの権限をすべて工場長が握っているとしたら、ライン長であるあなたが管理できるのは、せいぜい配員の時間調整ぐらいしか残っていません。
そういうライン長であるあなたに工場長が、「お前のラインのチャージ(時間当たり労務費)は高すぎる。何とかしろ!」と暴言じみた命令を発したところで、ライン長であるあなたにとって、部下の給料は所与の前提になっているため、できるだけ手待ちにならないように当番表に気を配る以外に対処法がないのは明らかです。
従来の「原価計算基準」の管理可能費については、上記のような「責任能力」の有無だけにフォーカスされていたと思います。例えば、生産物量の変動により生じてしまう「操業度差異」は、もはや生産部門の問題ではなく、製造指図量に強い影響を持つ受注数量を決める営業部門の責任である、という説明がまことしやかに叫ばれて、それが責任会計論のあるべき姿と思われてきました。
表面的には、そうなのですが、製販会議でのすり合わせを綿密に行い、需要変動に可能な限り対処して余剰生産能力のムダを最小限に抑制するのが大人の知恵であり、そういう努力は、営業部門と生産部門の連係プレーが不可欠なのです。そういう中で、責任能力だけに焦点を当てた責任会計論は、「絵に描いた餅」以上に現場に逆作用をもたらせます。やがて誰も操業度差異について真剣に解決しようとしない雰囲気が蔓延するのは火を見るより明らかです。
あまり、「誰」にこだわりすぎて、「どうやって」を忘れてしまうと期待する結果が得られないことが起きます。何か悪いことが起きたら、誰のせいか犯人を見つけるより、どうやったらリカバリできるかを考えたほうが前向きでかつ、組織のためになると断言します。「どうやるか」を真剣に考える過程で、自然と誰が犯人かが明確になります。信賞必罰も大事ですが、まずは火を消すことを優先しましょう。
大事な「回避可能性」を見落とすな
コストの管理可能性を考慮するとき、「②回避可能性」と「③影響力」も同時に考慮することが大事になります。「②回避可能性」は、そのコストの発生を意思決定した時点と、実際にそのコストが発生してしまうタイミング(期間)のズレが大きい場合、この時差をきちんと考慮しましょう、ということを意味しています。

上表は、特に、固定費を予算管理の技法の適用のしやすさで、3つに細分化したものになります。原価管理は予算管理の前提となる必要条件なので、これは原価管理にも共通の分類となります。
業種や企業が採用するビジネスモデルにも左右されるのですが、一般的に固定費のほとんどは、キャパシティ・コスト、中でもコミテッド・コストが大多数を占めます。ビジネスを実際に遂行するためには、先行投資(R&D、設備投資、従業員の訓練や採用、水道高熱等の公共サービスの手配)と呼ばれる、ビジネスを始める前に支出額を決めておかなければならず、時には、売上からのキャッシュ回収前に、身銭を切ってキャッシュアウトしなければならないコストが多く出てしまうものです。
確かに、生産ラインでどんな製品を作り、月産何台の生産能力を確保するか、そのために必要な材料仕入と工員の手配はどれくらい必要か、意思決定するタイミングでは、それらはすべて、意思決定者にとって、「管理可能費」だということができます。
しかし、いったん設備投資が実行された後、その設備投資がもたらす減価償却費は、当初の予定通りの製品の売れ行きでなくても、発生金額を回避することはできません。確かに、制度会計が求める全部原価計算によれば、生産設備から生じる減価償却費のほとんどは、製造固定費となり、当期の売上高と期末の棚卸資産に案分することができます。期末の棚卸評価にまわった減価償却費の今期の発生(この場合、P/Lの売上原価に計上されるとの意味)を免れることができます。
ですが、それは製品が実際に販売されるまで費用の発生が繰り延べられているにすぎず、いつかはP/L上のコストとして認識する必要があります。仮に、永遠にその製品が売れることがないことが分かった場合、その時点で速やかに材料費を含むその棚卸評価額は損失(評価損)としてP/L計上する必要があります。
さらに、生産途中であっても、将来の販売見込みが著しく落ち込み、回復の兆しがないことが分かれば、その時点で即刻残っている未償却分は適正水準になるまで減損損失としてP/Lで落とす必要があります。
よくコンサルティングの現場で、「かんたんに管理可能費と管理不能費を勘定科目で仕分けてもらえませんか」と依頼されるのですが、軽々に引き受けることはしないのです。若かりし頃、予算管理担当者として、管理不能費と管理可能費を集計してレポートを作成していたこともあるのですが、形式的に勘定科目で区別してデータを集計することに後ろめたさを感じていたものです。
最後の切り札「影響力」
同じ直接工への支払い給与である直接労務費であったとしても、「①責任能力」の観点から、工場長にとって管理可能費であっても、ライン長にとっては管理不能費になるかもしれない、という可能性があることを説明しました。
これから新製品を生産する工場の新規生産計画立案時点では、そこでラインにつく正社員契約に基づいて配置する予定の直接工への支払い給与は、管理可能費ですが、実際に配置した後では、配置転換をしない限り、その支払い給与は管理不能費です。それは、「②回避可能性」によるものです。
では、「③影響力」とは一体どういうものでしょうか。それは意思決定者の判断により実際的にそのコストの発生時期と発生額をコントロールできるのかという問題に帰結します。
仕入材料費等は、個別費、変動費扱いしている企業も多いと思います。ここで、あなたが日頃取引しているサプライヤーが大変競争力を持った素材を提供しているとして、競合他社に買い負けないように、他社より有利な購入条件として、1か月の仕入数量の最低ラインを保障し、最低発注数量を実際発注数量が下回った分は保障することを約束していたと仮定します。
単価10円で、100個の最低発注量(月当たり)を約束していますが、通常は発注数量が軽く100個を超えているので、その場合には、購入数量に単価10円をかける変動費扱い、すなわち管理可能費扱いで原価管理しても何の不都合も生じません。
しかし、いったん、月の最低発注量の100個を下回った場合、例えば、50個しか発注しなかったとしたら、
@10×40個=400円の変動費(管理可能費)にプラスして、@10×60個=600円の「準絶対的固定費:Absolute Cost」を負わなければなりません。
変動費や固定費の詳しい分類については、次の記事を参考にしてください。
これと同じ状況になりがちなものには、手付金契約、エージェントとの定期契約、前期の外形標準で決定される税金等が該当します。ですから、勘定科目だけに基づいて管理可能費と管理不能費をシンプルに区分けできるという幻想は捨てたほうがよさそうです。
えっ、自分で管理可能費と管理不能費を都度判断する自信がないって???
そういう場合は、筆者を呼びつけてください。喜んで馳せ参じます。^^;)
みなさんからご意見があれば是非伺いたいです。右サイドバーのお問い合わせ欄からメール頂けると幸いです。メールが面倒な方は、記事下のコメント欄(匿名可)からご意見頂けると嬉しいです。^^)
(注)職業倫理の問題から、公開情報に基づいた記述に徹します。また、それに対する意見表明はあくまで個人的なものであり、過去及び現在を問わず、筆者が属するいかなる組織・団体の見解とも無関係です。




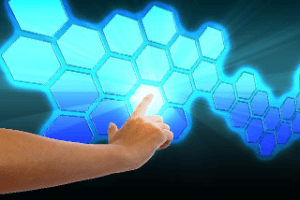
コメント