変動費と固定費に分ける目的
操業度との関連において、原価要素を操業度に対して比例的に変動する意味で「変動費」、操業度の大小(高低)にかかわらず発生額が一定(固定されている)ものを「固定費」と区別することを前回確認しました。では、なぜ原価要素を「変動費」と「固定費」に大別するのでしょうか?
それは、経営者が「損益分岐点分析」または「CVP分析(Cost Volume Profit Analysis)」というツールを用いて、コストと利益を管理できるようにするためです。損益分岐点は、BEP(Break-even Point)とよくあるアルファベット3文字略称で呼ばれたりもするので、この際、CVPとBEPは合わせて覚えておくことにしましょう。

上図には、いくつかのお約束がありまして、売上線は角度45度で引いてください。ケインズ経済学の「45度線分析」から着想を得ているモデルだからです。そして、操業度は売上を変数と置きます。売上は金額(すなわち売上高)か、数量(すなわち売上数量)のいずれで表現するかを決めます。
計量単位がことなるセールスミックスをひとつのCVP分析チャートで表現するためには、金額表示の一択しかありえません。計量単位がひとつ(個、トン、メートルなど)に限定できる場合は、売上の計量単位(販売数量mなど)でも操業度を表現することができます。金額表示しない場合は、45度線の制約は逃れることができます。
詳しくは、下記の関連記事をごらんください。
とどのつまり、損益分岐点または、損益分岐点売上高を図示することで、単年度予算の策定や、期中の損益予測に役立てることが、CVP分析の目的です。損益分岐点を知ることができれば、経営者は、現状分析や来年度の業績予測を行う際に、短期的な利益目標を達成するために、
- 売上が足りない
- 変動費が計画(または見込)からズレている
- 固定費が予想外に膨らんでいる
という利益関数に含まれる3つの変数のうち、どれがいけてないのかを知る手掛かりになるからです。
固変分解(原価分解)とは
まず入手したい情報が何か(what)を先に知りました。それは変動費と固定費という分類です。次の問題は、この分類をどうやって行うか(How)、です。
そもそも、「原価分解」と呼ばれていたこの作業は、現在は「固変分解」と呼称される機会の方が増えています。その理由は、「原価分解」を真面目にやると、「準変動費」「準固定費」などが洗い出されることになります。しかし、「CVP分析」をこれまでのITの制約を考慮すると、会計実務的にはたったひとつの1次関数でC-V-Pの相関を見るのが関の山だった時代が久しくありました。
そこで、実用的な解として、思い切って「変動費」と「固定費」の2分法を採り、上記のようなたったひとつの1次関数で、C-V-Pの相関を見るようになったのです。決まって、「変動費」と「固定費」の2種類しか識別しなくなったので、「原価分解」という用語が次第に「固変分解」と呼ばれるようになったのです。
ちなみに、現在はExcelなど、原価管理の現場でコスト分析を担当する文系出身者であっても、意外なほど簡単に多変量解析できる時代になりましたので、筆者もコンサルティング実務では、複数の高次関数を組み合わせて利益予測を行っております。^^)
教科書には「What」はいろいろと記述してありますが、「Why」が書いてあることは稀です。なぜなら、「Why」に紙幅を割くくらいだったら、実用的なwhat情報を少しでも記述しないと著書が売れない時代になっているからです。便利さや効率的であることを追求しすぎると、ものごとの根本をおろそかにしてしまい、逆説的に心理から遠ざかることはよくあることです。
この「原価計算基準」解説シリーズも回を重ねること、今回で28回目ですが、47分の8も終わっていません(消化率:17%)。このペースだと、最後の「47 原価差異の会計処理」に到達するまでに、単純計算で後116回の解説が必要になります。気が遠くなります。^^)
固変分解(原価分解)の手法
すでに、変動費と固定費を個別に求めるという観察行為自身が、変動費と固定費をどのように定義するのかを含んでしまいます。これが意味するところは、変動費と固定費の2つ以上の求め方があった場合、同じ結果をもたらすことは偶然の一致を除いて期待できないということです。
それでも、その手法の違いを求めてこの説明を忍耐強く読んで頂いている読者の期待に応えるために、できるだけ簡潔に相違とプロコンを試みてみます。

IE(Industrial Engineering )法:
テイラーよろしく、動作研究や時間研究を通じて、生産要素の投入と製品の産出の間の比例的な関係を求めます。これは、標準原価計算における科学的な手法による原価標準を求めることと同義です。大事なポイントは、①将来のコストを生産技術面から分析して予測すること、②会計データだけではなく、生産技術の工学的な計算処理を必要する、という所です。
メリットは、客観的なデータを得ることができますが、一方でデータを得るのに多大なコストが発生すること、そして、直接材料費や直接労務費など、産出される製品と直接結びつけられる活動費は正確に測定することができますが、製造間接費と製品産出高の間の相関関係を得るには、幾重にも仮定を置かざるを得ず、精度が極端に落ちるところです。
「ヒストリカルデータ予測法」は、過去実績のコスト情報と操業度情報の関係から将来のコストと操業度の相関関係を導こうとする手法の総称です。当然、過去データに依拠することは、過去からの連続線の上に将来があることが大前提になっています。
費目別精査法(勘定科目精査法):
特定の測定期間(月、四半期、年)、コストと操業度の相関を観察し、人間の判断で、固変を仕分ける閾値(しきいち)を設けて、その値を越えたら変動費、越えなかったら固定費というふうに、科目ごとに固変分解をする手法です。
メリットは、勘定科目ごとに固変が判定されることになるので、予算統制や目標管理制度と結びつけることで、容易にコスト管理の仕組みに組み込むことができることです。例えば、直接材料費と直接経費だけを変動費とし、他は全て加工費として固定費扱いする、という分かりやすい分類です。
デメリットは、準変動費や準固定費を乱暴に固変いずれかに分類することが、全体コストの操業度との比例関係を損なっているという批判に反論できないところです。厳密な数学的には、間違っているが、実務慣行的には便利さゆえに許容されている、という感じです。
スキャッター・チャート法(スキャッター・グラフ法):
まだ、ITが発達していなかった時代の名残として、縦軸に総コスト(ここでは変動費と固定費の総額)、横軸に操業度という散布図(スキャッター・チャート/グラフ)を紙に書き出して、点の集合の上に手書きでコスト線を引くことで、手書き線の傾きが「変動費率」、手書き線とY軸との交点と原点の長さを「固定費」発生額と仮定するものです。
この手法は後に続くものに共通していますが、総コストをある数学的な特徴を用いて変動費と固定費に分解するものなので、人間の判断(人間の判断で重みづけられた閾値での分類含む)でえいやーと固変分解するより、数学的には有意なクラス分けと支持者には考えられています。
「手書き」という点がノスタルジックな感傷を呼ぶのですが、Excelなどのツールが容易に使える現代において、下記のより厳密な数学的手法が存在していますので、この手法の歴史的使命はもう終わったと思います。
単純高低点法:
スキャッター・チャート法はグラフで固変問題を解くのですが、こちらは数式で解きます。観測点(例えば月末)ごとの、操業度(X)と総コスト(Y)の組み合わせを抽出します。(X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3), (X4, Y4),,,
この時、(X1, Y1)が最小点で、 (X4, Y4)が最大点だった場合、
(X4 – X1)/(Y4 – Y1)がコスト線の傾き=変動費率として求まり、このコスト線がY軸と交わるときの切片を固定費発生額とします。
メリットは、手書き線で傾きと切片を求めるより、数学的にはより厳密なことです。ですが、高低点がもしかすると、それぞれ異常値とか外れ値だった場合、過大または過小な傾きとなりますので、その点では実務的でないと批判されることがあります。
調整高低点法:
そこで、直線の傾きと切片を計算で求める際の最小点および最大点のそれぞれから異常値と外れ値を除いた正常値を用いるのがこの手法です。まず簡便法として、常に観測期間の最大値と最小値を機械的に除いて、2番目に大きい値と2番目に小さい値を高低点に採用する方法がまず導入されました。現代ならば、統計的な手法(スミルノフ=グラブス検定、クラスター分析など)を用いてExcel等で簡単に統計学的に有意な解を求めることができます。時代の趨勢を感じさせます。
回帰分析法:
ここまできますと、もはや統計学のフレームワークで解くしかなくなるので、回帰分析の中でも、最も基本的で簡潔である最小二乗法に基づく単回帰分析で、近似値としての総コスト直線を求めるという手法が一般的になりました。
ただし、今やリニアプログラミング(線形計画法)の様々な手法が原価管理の世界にも取り入れられています。もはや、最小二乗法による単回帰分析の独壇場ではなくなりつつあります。単回帰分析につきましては、下記の関連記事もご参考ください。
結局、どの固変分解が正しいのか
どの固変分解が正しいか、ではなく、どの局面で、どういう使い方をするかをまず問わなければなりません。
仮に、社内の原価予測や予算策定に使いたいという趣旨なら、「費目別精査法(勘定科目精査法)」をお勧めします。費目(勘定科目)の分類基準や詳細度にも依りますが、勘定科目ごとに固変分解されていた方が、予測や計画も立てやすいでしょう。
勘定科目ごとに積み上げることもできるし、購買とか加工とか販売などの活動量を調整すれば、それに従って、材料費・在庫費、労務費・減価償却費、販管費などの変動が予測しやすくなるからです。
一方で、外部から競合他社の財務分析のために、複数社を比較可能にしたままパネル分析したい場合は、外から観察できる操業度(売上高)と総コスト(売上原価+販管費)という変数は共通ですので、最小二乗法という共通の解析ツールを用いれば、比較可能なデータが得られることを良しとします。
また、社内使用目的であっても、中期事業計画等、ある程度抽象的な財務モデリングで中長期の損益・原価予測を立てる場合は、「費目別精査法」以外のヒストリカルデータを用いた統計的な固変分解の手法を活用されることをお勧めします。
コンサルタントの本音としては、精緻な固変分解データより、コスト政策に基づく操作性の高い固変分解データの方に軍配を上げます。コスト政策に対する感応度が大きく、とある政策を採用すると、いくらぐらいコストが下がるか、または操業度が上昇するのかの見通しがつく方が、いくら統計学的に精緻であると主張されても、それで飯が食えるようになるか、という反論をついしてしまいます。^^;)
経営のために管理会計があるのであって、管理会計のために経営があるのではないので。
最後におまけですが、売上高から変動費を引いた利益を貴社ではどのように命名されていますか?
「限界利益(Marginal Profit)」というネーミングが一番好まれているという実感を持っています。しかしながら、これは、ミクロ経済学からの借用語であり、収入から限界費用を差し引いたものをそう呼んだことにちなんでいます。
管理会計畑の人ならば、同じ概念を適切に、「貢献利益(Contribution Margin)」と呼んでいただきたいものです。売上から引くのは変動費であって限界費用ではないので、固定費を回収してさらに営業利益を稼ぐのに貢献してくれる利益としての「貢献利益」の方が、CVP分析の管理目的にふさわしいと感じているからです。なんだったら、「変動費」を差し引くので、「変動利益」と呼ぶ方が限界利益よりいくらかましです。まあ、どちらでも構いませんが、ちょっとしたこだわりです。^^;)
参考記事 言葉を大切にするコンサルティング(1)用語を適切に使い分ける
みなさんからご意見があれば是非伺いたいです。右サイドバーのお問い合わせ欄からメール頂けると幸いです。メールが面倒な方は、記事下のコメント欄(匿名可)からご意見頂けると嬉しいです。^^)
参考記事 原価計算基準(原文)




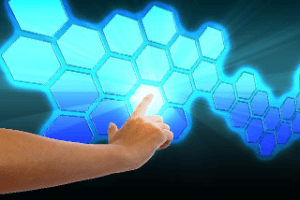
コメント