■ 管理会計・財務分析の最有力派閥のひとつ、「CVP分析」を斬る!

筆者が管理会計に魅せられて、既に四半世紀が経ってしまいました。その中でも、「CVP分析」と「デュポンチャート」に出会った青春時代は今でも忘れられない思い出です。そのうちに、「EVA:Economic Value Added(経済的付加価値)<スターン・スチュワート社の登録商標>」と「DCF:Discounted Cash Flow」に出会ったのが管理会計人生の第2の衝撃波でした。
これから延々と「CVP分析」について語り始めるのですが、最初に読者の方(特に管理会計初心者)に襟を正して、お断りしておかなければならないことがあります。それは、数学的な理論背景を持ってCVP分析を凌駕する(というより完全否定する)複利計算による原価計算と操業度分析の理論がすでに存在することです。
● 公認会計士高田直芳 会計雑学講座とサバイバル経営戦略の後日談
しかしながら、高田氏も言及しているように、やはり管理会計はCVP分析を一度は学ばないと、キャパシティコスト、貢献利益・限界利益、直接原価計算などといった概念を理解することはできません。また、上場企業にとって、決算短信における業績修正のトリガーが、未だに、売上高の乖離が±10%で、段階利益の乖離が±30%、と各業界一定の閾値になっていることの背景理解のためにも、CVP分析の学習の必要性がまだ十分にあると考えています。
高田氏によれば、「CVP分析」は、アメリカ人のヘス(C. Hess)が1903年に考案し、同アメリカ人のノイッペル(C. Knoeppel)が1920年にCVP図表を作成したのが起源とされており、いまや誕生から110年以上経っています。「デュポンチャート」の方も、1919年に、米国の化学会社E.I.デュポン社によって考案された財務管理システムで、こちらも誕生から100年近く経っています。こちらも、途中で「EPSツリー」、「DOEツリー」や「ROICツリー」といった応用編が編み出されており、順当な進化を遂げているともいえます。
それゆえ、筆者のCVP分析の学習と実務での応用についての集大成として、このシリーズを始めても十分に意義があるのではと考える次第です。
■ 「CVP分析」の基本概念と活用シーンを説明させて頂きます!
前置きが少々長くなりました。いよいよ、本題に入ります。漫然と「CVP分析」という言葉を何度も使っていますが、この語は、「Cost – Volume – Profit analysis」の省略・訳語で、企業の損益状態を、①コストの発生状態、②営業活動量の大小、の2つで説明できるようにするものです。
その損益状態のうち、黒字でも赤字でもない収支トントンの売上だったり、操業度だったりするケースのことを、「損益分岐点」といいます。営業活動量(その設定方式は後で説明します)を直線で示して、その線分上の収支トントンのただ一点が求まるものとする理論なので、「点」と表記します。「CVP分析」で説明される損益状態のうち、収支トントンという唯一の特殊解が「損益分岐点」。その点を求めることを「損益分岐点分析」と呼ぶことから、一般的には、「損益分岐点分析」は「CVP分析」に包含されます。「損益分岐点」とは、「BEP:Break-even Point」の和訳になります。
では、「CVP分析」は経営管理・財務分析のどういった領域、シーンで必要とされるのでしょうか。教科書的には、通説として、「短期利益計画」に使用するものである、とされます。「短期利益計画」とは、「単年度予算編成」と「単年度予算統制」のメインどころです。多くの企業が高田氏の指摘にもかかわらず、向こう1年の利益計画を立てる際に、CVP分析手法を用いて、予算上の目標利益を定めます。そして、1年間の会計期間を過ごす間、固定費を回収するためにどれだけの販売量を維持するか、個別受注生産の会社ならば、この受注はどれだけ値引しても利益が出るか、いろいろな損益決定につながる経営的意思決定にも活用します。
つまり、年度予算の立案、実績計上による予実差異分析と期末損益着地点分析といった、年度目標達成のためのPDCAツールとして使用されることを前提としています。
■ 「CVP分析」が有効なツールである前提条件とは?
年度予算の立案と統制(目標達成に必要な補正活動の指針とするの意)に「CVP分析」が有効であり続ける前提条件は、コスト(C:Cost)と、営業活動量(V:Volume)と利益(P:Profit)の関係が、一定・不変であることです。
<CVP分析が有効である前提条件>
(1)CVP分析モデルが確定モデルである
将来の企業活動によって生じる収益および費用は、確実に予測できること。
→モンテカルロ法や、リアルオプション法などを使用した統計確率的なシミュレーション手法ではない。
(2)CVP分析モデルは1次関数モデルである
CVPの関係は線形モデル(1次関数モデル)が維持されていること。
→正常操業度の範囲内においては、製品一単位当たりの販売単価、原価単価は一定であるとの仮定を置く。すべての売上やコストは直線で図示される。
(3)原価計算は「直接原価計算」の採用を仮定する
コストは、営業活動量の増減に比例的に発生する「変動費」と、営業活動量の大小を問わず一定額のみ発生する「固定費」とに2分されること。
→全部原価計算における在庫増減の影響がない(生産量と販売量が同じ)という仮定をおく。
<筆者の庇いだて>
(1)について
CVP分析は、「感度分析」といって、確定モデルの前提条件が変わったら、その変数を予期する値に変更して繰り返し損益予測することができるため、線形モデルという制約下であるものの、将来予測の変動に合わせたシミュレーションができる。
(2)について
貢献利益図法において、セールスミックス(プロダクトミックス)の違いによる複数の利益率の製品の最適組み合わせ問題も解くことができるため、線形モデルの制約を一部突破したシミュレーションが可能になる(後の回でこの手法を解説します)。
(3)について
そもそも在庫増減を考慮しなくてはいけないケースに適用できないことで、この分析の価値が下がるとは思わない。制度会計における業績予測には別の手法を充てるべき。逆に、全部原価計算に基づく期間損益計算結果が、真の業績を表示しているとは限らない。
■ 「CVP分析」の基本モデルを解説します
(1)数式モデル
数式モデルを考える前に、「営業活動量」を表す指標を決めなくてはなりません。一般には、下記のような指標を用います。
・売上金額
・売上数量
・生産金額
・生産数量
・操業度(操業時間・稼働時間)
・売り場面積
・工数
売上高と変動費について、単位当たりの金額変化がつかめるのなら、理論上はどれでも構いません。つまり、計算技法として「変動費率」や、「変動費単価」がつくれるのならどれでも構わない、という意味です。前章の前提(3)にある通り、在庫増減を想定しないこと、販売活動量の結果としての利益を考えた方が、生産活動量の利益を考えるより結果思考であることから、生産基準より販売基準の売上高または売上数量を用いた方が、利益を考えるのにはより適切かもしれません。もちろん、生産工場が生み出す利益を「CVP分析」したくなるケースの実務上あり得るので、そういう場合は生産高基準の指標を使用することもありますが。
ということで、「売上金額」と「売上数量」の2つを使った数式モデルを紹介します。操業度、面積、工数など、金額指標でない類のものは、「売上数量」モデルを応用すれば実現可能です。
①「売上金額」ベース
売上高 = 変動費 + 固定費 + 利益
=(変動費率 × 売上高) + 固定費 + 利益
ここで、
S:売上高
α:変動費率(売上高変動費比率、変動費比率)
F:固定費
P:利益
とおくと、
S = α × S + F + P
(1 - α)S = F + P
S = (F + P)÷ (1 - α)
と式を変換することができます。
この時、次の条件を満たす売上高(S)を求めたい場合、
・固定費(F):1000
・変動費率(α):40%
・目標利益(P):500
S =(1000 + 500)÷(1 - 0.4)
= 1500 ÷ 0.6
= 2500
という感じで、所与のコスト発生条件下で、さらに目標利益が設定された場合に、その目標利益を達成するために必要な売上高がいくらなのかは、この数式モデルに、各条件値を代入することで求められます。
ここで、(1 - α)が意味するところを考えてみましょう。αは、売上金額に対して、40%だけ変動費が含まれていることを示す「売上高」に占める「変動費」の構成比率です。これを「1」から差し引いた数字は、「売上高」から「変動費」だけを差し引いた「利益」の「売上高」に占める割合を示すことになります。この「利益」を、「CVP分析」の世界では、「限界利益(Marginal profit)」「変動利益(Variable profit とは聞きなれませんが)」「貢献利益(Contribution margin)」と呼びます。英語圏では、「Marginal profit」「Contribution margin」がメジャーですが、ミクロ経済学の「限界概念」との混同を避けて、日本では「変動利益」の語を好む人もいます。ですが、ここではそういう通好みの呼び名があることは予備知識として持っておくとして、一番耳にする「限界利益(MP)」の語を採用することにします。
売上高 - 変動費 = 限界利益
となり、売上金額の1単位、すなわち1円当たり、限界利益が占める比率を、限界利益率(m)と置いた場合、
(1 - α)S = F + P という式は、
m × S = F + P
S =(F + P)÷ m
日本語に置き換えると、
売上高 =(固定費 + 利益)÷ 限界利益率
となり、「固定費」と「限界利益率」が所与の前提で、「利益」の部分に「目標利益額」を代入することで、「目標利益」を達成するのに必要な「売上高」を求める式を手元に置くことができました。
「(1)数式モデル 」「①「売上金額」ベース」と、章立てしているので、(2)とか②とか、当然用意していたのですが、どうも基本概念を説明しながらの解説だったため、ここまでで文字数をかなり消費してしまいました。続きは、次の投稿で。(^^;)

⇒「CVP分析/損益分岐点分析(2)基本モデルを理解する - 数式モデルの成り立ちについて」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(3)基本モデルを理解する - チャートモデルで可視化 」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(4)チャートモデルを味わい尽くす - ビジネスモデル分析や利益モデリングを試みる!」
⇒「CVP分析/損益分岐点分析(5)変動費型モデルと固定費型モデルの違い - 決算短信における業績予想の修正のカラクリ」


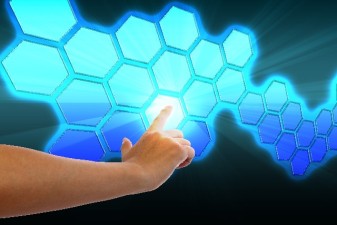
コメント