Criteria for Classifying Leases リース取引の分類基準
のっけからペースを崩されてしまいましたが、米国では2018年12月16日以上開始する事業年度より、新しいリース基準が適用され、USCMAの試験では、2020年1月より新基準対応の問題となります。私が受講したWebコースは、2019年4月17日配信のものなので、テキストも旧基準をせつめいしてから、新基準をおまけな感じで解説されていました。
ここでは、新基準ベースでサブノートをまとめていきたいと思います。もちろん、新旧対比表的なまとめは無しの方向で。^^)
リース会計をよくご存じの方もそうでない方も、何をおいても、リース取引を「オペレーティング・リース」と「ファイナンス・リース」に分類するところから始まります。なぜなら、その種類分け次第では、賃貸借取引に擬して処理するか、売買取引に擬して処理するか、大きく会計処理が異なってくるからです。
| # | 項目 | 説明 | 分類 | for the lessor | 貸手条件 | for the lessee | 借手条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Transfer of ownership | 所有権が lessee に移転 |
所有権 |
Sales-type lease | ①~⑤のひとつでも満たす | Finance lease | ①~⑤のひとつでも満たす |
| ② | Bargain purchase option | 割安購入選択権が付与され、 行使が合理的に見込まれる |
|||||
| ③ | Lease term | リース期間が useful life の75%目安 | 所有権 移転なし |
||||
| ④ | PV of Lease Payments | リース料総額と保証された残存価額の PVがリース物件のFMVの90%目安 |
|||||
| ⑤ | Specialized asset | リース期間終了時に貸し手にとって 代替的な用途がない |
|||||
| ⑥ | PV of Lease Payments | ④に加え、第三者が保証する残存価額 |
Direct financing lease ⑥⑦両方満たす |
Operating lease ⑥⑦両方満たさない |
Operating lease | ①~⑤のひとつも満たさない | |
| ⑦ | Collectibility of LPs | 貸手が全額を回収する可能性が高い |
⑥において、「④に加え第三者の保証する場合が加えられる」について補足説明。例えば、メーカーが自社品をリースで顧客に提供する場合、リース物件返却時に残存価値を保証するのは借手(lessee)のみ。しかし、メーカーが販売して、リース会社(メーカーのグループ会社の場合を含む)が借手へリースする場合、メーカーに対して、借手以外のリース会社(lessor)が残存価値を保証するので、ここで第三者が加えらえています。まあ、ここまではいいんじゃないかな。^^;)
リース取引の構成要件
リース取引を構成する要素
- Lease payments(リース料総額)
- Contractual fixed payments(固定リース料)
- Variable payments(if any)(物価変動等を考慮した変動リース料)
- Bargain purchase option(if any)(割安購入選択権:リース終了後の買戻し時の話)
- Guaranteed residual value(if any)(保証残存価額:貸手が返却時に補填を約束)
- Termination penalties(if any)(解約に伴う違約金)
- executory costs(リース料に含まれずに lessee が毎年負担する金額、発生時に費用化)
- insurance
- property taxes
- maintenance
Finance lease 借手側
Finance lease は、lessee にとって、リース物件を割賦購入取引、または借入資金での購入として、物件購入取引と借入資金の返済取引が合成されたものと理解することができます。経済的実態として、リース物件を購入したものと考えます。
取得日(リース開始日)の会計処理
【Example】
lease term: X3年1月1日~X5年12月31日(3年間)
Fixed payments: 毎期末に支払400
Discount rate: 10%
所有権が移転しない Finance lease
原資産の耐用年数は3年
Commencement day(リース開始日)に、lease liability(リース負債)は、present value of lease payments で計上します。将来払っていくリース料は利息込みの金額であり、リース開始日には、利息部分を除いた元本部分だけを負債計上するためです。
使用する割引率は、下記の通り。ここは新旧変更点。
- The rate implicit in the lease:リース料+無保証の残存価額の現在価値と原資産の公正価値と貸手の初期直接コストの合計を等しくする率←原則
- leasee’s incremental borrowing rate:lessee が、仮に lease asset を自己資金で借入にて購入するとしたら、採用する利子率←原則が採れないとき
まだ、割引率の話題は続いて、期末払い(後払い)の場合は、Ordinary annuity、期首払い(前払い)の場合は、Annuity due の年金現価係数を使用します。上記例題は前者。よって、期間3年10%の年金現価係数は、2.48685 なので、
annual rent = 400 × 2.48685 = 995
| account | debit | account | credit |
|---|---|---|---|
| Right of use asset | 995 | Lease liability | 995 |
リース料支払い時、決算時の会計処理
リース開始日に、計上した right of use(使用権資産)は、リース負債の現在価値なので、毎期の支払いリース料は元本返済部分と利息支払い部分とに分解し、元本返済部分のみの金額で、リース負債のその時の現在価値から控除していく必要があります。
社債、投資の所で学習した、effective interest method(利息法)を用いて、
Interest expense = lease liability のその期の残高 × Interest rate で経年に従って計算します。
| 年度 |
期首債務額 |
利息発生額 ②=①×10% |
支払額 ③ |
債務返済額 ④=③-② |
期末債務額 ⑤=①-④ |
|---|---|---|---|---|---|
| X3 | 995 | 99 | 400 | 301 | 694 |
| X4 | 694 | 69 | 400 | 331 | 363 |
| X5 | 363 | 37 | 400 | 363 | 0 |
| 合計 | – | 205 | 1200 | 995 | – |
このリース資産(厳密には right of use)の現在価値が995で、その将来価値が1200。1200の内訳は、元本部分の現在価値995とそれに伴う利払いの将来価値合計205に分解されます。
これでリース料支払い側の処理の準備はOK。
Finance lease は購入取引に擬して処理されるので、同時に、資産計上とその償却計算も行う必要があります。所有権が移転するケースは、通常の購入したケースと同様に、原資産の useful life にわたって、amortization すれば大丈夫。所有権が移転しないケースは、原資産の耐用年数とリース期間のいずれか短い期間で償却します。
償却期間と残存価額について、所有権が移転しないケースには、リース物件満期返却時に、残存価値を保証するかどうかのオプションがついていることがあり、それがアリとした場合、下図のように整理されます。テレコになっているだけですが。
| 所有権が移転する | 所有権が移転しない | ||
|---|---|---|---|
| Depreciation period | 通常の耐用年数 | 通常の耐用年数orリース期間短いほう | |
| Residual value | Guaranteed residual value | – | 保証した金額 |
| Unguaranteed residual value | 見積金額 | ゼロ(控除しない) | |
よって、例えば、X4年12月31日の仕訳は、次のようになります。
| account | debit | account | credit |
|---|---|---|---|
| Interest expense | 69 | Cash | 400 |
| Lease liability | 331 | ||
| Amortization expense | 332 | Accumulated amortization | 332 |
ここまで、リース会計と、所有権が移転しない finance lease の借手における会計処理まで見てきました。次回は、それぞれのケースでの仕訳の切り方を比較しながら全体の会計処理の理解を進めていきたいと思います。



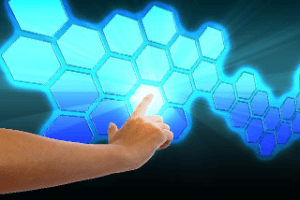
コメント